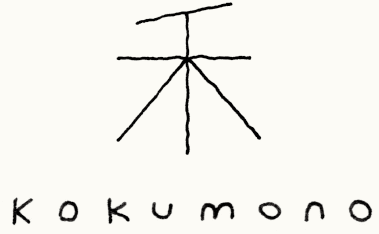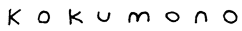大豆を煮るということ
2025年01月29日
大豆を煮るのはめんどうだなーとつい思ってしまう私。一晩水につけてから翌日煮る、ということは翌日の気分まで考えないといけません。今日大豆を食べたい煮たいと思っても明日まで待たないといけない、今日水につけてしまえば明日には煮ないといけない…。そんなことを繰り返し考えてしまうからめんどうくさいと思ってしまうのです。大豆を栽培していても家で煮ることはほとんど(本当は全く…)ありません。味噌作りも、藤原みそこうじ店さんに出会ってから藤原さんの味噌が美味しくって数年前の手作り味噌がなかなか減らなくなり、家では作らなくなりました。一方小豆は洗ってすぐに煮ることができます。そしてその日中に食べられる。食べたいなーと思ったその日に出来るのでさくさくっとことが進んで嬉しい気持ちに。夫が小豆作ってくれないかなと思っています。大豆を必要としてくださる方がたくさんいる一方で、横着なこと言っていてごめんなさい。
そんな大豆を最近は鶏のために煮ています。冬になると魚を獲れる量が減るからか、スーパーからいただく魚のあらの量が減ります。そうするとタンパク質の量がやや不足気味。過去の経験から大豆がその代わりになるのはちょっと厳しいと思いつつ、微々たる改善でもいいから何かした方がいいなと思って大豆をあげることに。
そうして、数年放置していたクズ大豆を引っ張り出してきました。なんだかちょっとかびてるし、砂っぽいし、これ大丈夫かなと思いつつ、明日絶対に煮るぞ!という強い気持ちで一晩水につけます。
翌日はやっぱりちょっと重い気持ちでその大豆を見つめるのですが、ぱんぱんに水を含んだ大豆を見ると随分大きくなりましたね!とちょっと感動します。そして煮始めると、だんだんだんだん、美味しそうなお豆が現れるのです。クズ大豆、煮てしまえばスッキリ綺麗!と心の中で唱えたくなるほど、クズとは思えない艶やかさ。
茹で上がった大豆は味噌作りの時のように潰します。以前はこの潰す作業は足でやっていて億劫だったのですが、マキタの攪拌機を導入したらちょっと楽になりました。
他の餌の材料と一緒に発酵飼料に混ぜて山にしてむしろを被せればおしまい。しっかり餌の準備ができたなと誇らしげな気持ちになります。そうして最後には、小豆もいいけどやっぱり大豆は必要だな、今年も夫に作ってもらおうと思います。そんなことを週に1回、冬の日々です。
近藤温子
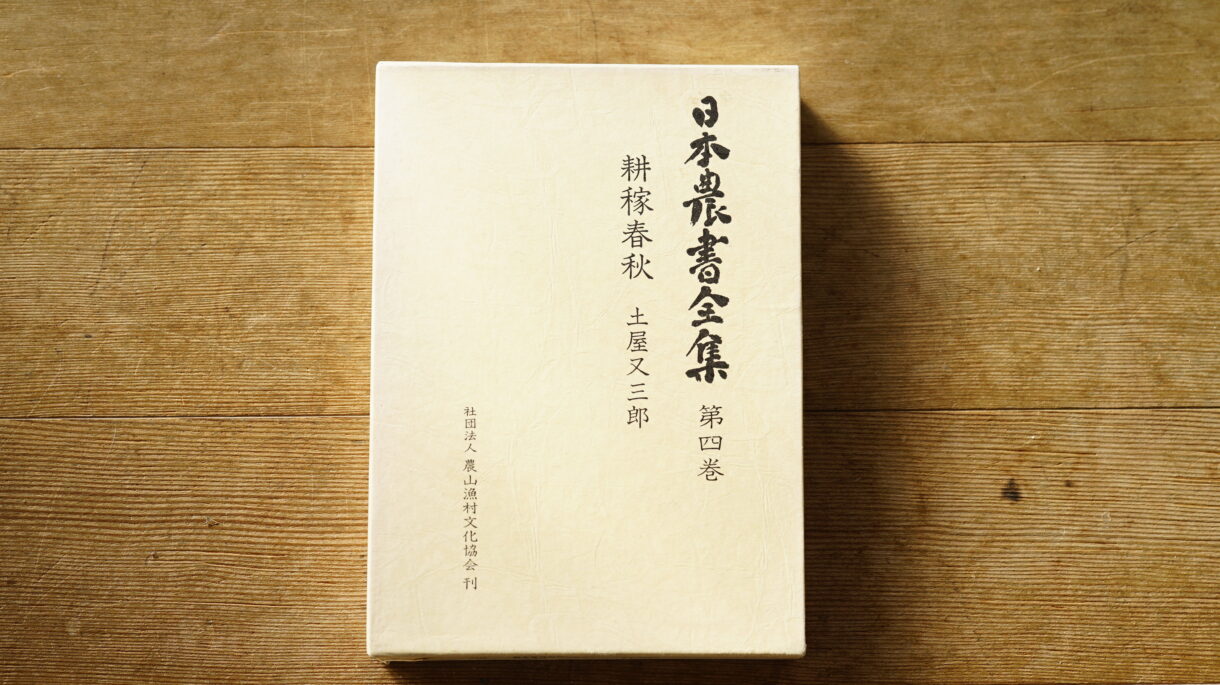
[1]江戸時代の水田は色彩豊かであったということ
2024年12月28日
|書籍
書名:耕稼春秋(日本農業書全集4巻)
著者:土屋又三郎
発行:農山漁村文化協会
|書籍紹介
耕稼春秋(こうかしゅんじゅう)は江戸時代の1707年に、加賀藩(石川県)の土屋又三郎が農民たちに向けて書いたものです。この日本農書全集第4巻は耕稼春秋の全7巻とその解題が掲載されていて、すべて現代語訳で読むことができます。
当時の北陸はこうした農書の多い地方として知られていました。それは全国的にみれば農業の先進地に及ばない中間地として、新しい技術段階に入った者と古い技術段階にとどまる者との格差が大きかったことを意味しているそうです。
加賀藩では武士が農村を支配するのではなく、百姓の有力者に村々の管理を委ねていました。その役職を十村(とそん)といいます。祖父の代から十村を勤める家に生まれた又三郎もまた、おもに農業の生産指導を担っていました。そうして30年がたった1694年、詳細な記録のない事件ののちに、又三郎は十村を解任、平百姓に格下げ、ほどなくして髪を剃って隠居しその23年後に死去しました。
又三郎は十村を勤めているあいだから農事研究の意欲を持っていて、精農や古老から教わったり自らも実践を繰り返したりしていました。そんな彼が時間的余裕のある剃髪生活のなかで書き上げた、後世に名を残す農書のひとつがこの耕稼春秋です。
全7巻からなる本書は、1697年に公刊された大著『農業全書』に大きく影響されていて、栽培法や農事暦からはじまり、田の面積の計算方法から税計算といった行政知識まで、幅広く取り扱われています。これは農民の知識や技術を向上させたい藩の方針のもとで、各地域の十村や上農を中核農家として指導力を発揮させるよう再教育することが目的だったと言われています。
|なぜ手に取ったか
数年前、たまたま目があった一冊の本を地元の図書館で手にとりました。『江戸日本の転換点 水田の激増は何をもたらしたか』という本です。戦国の世があけてから概ね平穏とよべる江戸時代になり循環型のエコな社会を築いた、という一般のイメージに対し、実態は持続可能性のほころびのようなものがそのときすでに深層には流れていたのではないか、そんな提言が書かれた一冊でした。
そのなかで、個人的にわたしが一番驚いたのは第一章「米の多様性」という12ページです。端的にいえば、「かつての田んぼは色とりどりであった」ことが書かれていました。そして、その重要な参考文献のひとつがこの耕稼春秋でした。なにかを学ぶならできるだけ原著にあたりたいと思っていて、最近ようやく手にすることができました。
耕稼春秋には宝永年間(1704-1711)ごろの石川郡における米の品種が記されています。収穫時期の違いからくる早稲、中稲、晩稲の3分類があり、その数は合計で82品種ありました。そして耕稼春秋が著されてから30年ほど経ったころに『郡方産物帳』という書物を加賀藩がまとめています。史料館にお願いをして原著のコピーをいただいたものの自分には読めなかったのですが、そこには品種名 / 芒(のげ)という穂先の毛の有無 / 籾の色 / 芒の色 / 味 / 収穫期間といった6項目が記されているそうです。記載された112品種のうち、55品種の籾の色は白 / 薄白 / 黄白といった今でも一般に目にしているもので、残りの57品種は赤 / 薄赤 / 赤黒 / 黒 / 薄黒といったものでした。そして半数以上のお米には芒があり、その色もまたさまざまだったようです。
また『江戸時代中期における諸藩の農作物 - 享保・元文 諸国産物帳から -』は圧巻の史料でした。簡単に紹介すると、享保20年(1735年)から元文3-4年(1738-1739年)にかけて、全国の大名領などでそれぞれの産物を調べた「産物帳」が編纂されたそうです。それらの中で保存がされていた一部(編者曰くおおよそ1/3)に記載のあった農作物の名前がひたすら書かれている書物です。稲に限らず野菜も果樹もあり、ただただ驚きの一冊でした。そこでは白 / 赤 / 黒のほかにも青の名がつく品種もほぼ全国的に確認できます。「青稲」、「青からぶんこ」、「青タチカルコ」などですが、緑という意味の青だったのかな、緑糯という古いお米は見たことがあるし、と勝手に想像しています。
それから、江戸時代よりも以前はどうだったのか。もしかしたら間違った理解かもしれないけれど、『森と田んぼの危機』によればもっと品種のバラつきは大きかったようです。具体的には、奈良・平城宮跡遺跡から出土した炭化米の標準偏差ばらつきはコシヒカリの5倍でした。そしてその5倍という数字は、明治時代にあった100の品種をランダムに取り出し炭化させたものと同程度だそうです。つまりそのエリアだけで100品種ほどあった、というわけではきっとないのだろうけど、それに近いという理解をしていいのかなと思いました。
水田を埋める稲穂の色は、一色ではなかった。「瑞穂の国」では、白い米だけでなく、赤や黒などもふくめた、バラエティに富んだ米が育てられていた。それが、開発期に広がった田園風景の現実の姿だったのだ。
『江戸日本の転換点』
|どう思ったか
「はじまりの味噌」というお味噌を、友人の藤原みそこうじ店さんと一緒につくっています。わたしたち禾の自然栽培のお米と大豆をつかって、藤原さん(わくさん)が野生麹菌と沖縄の海水塩で夏に仕込む玄米味噌です。
ここには2つの観点があって、1つは自然栽培と野生麹菌のつながり。野山にただよってきた菌たちがより馴染み好むのは、肥料や農薬といった現代技術で育ったものではなく、その土地の力だけで育ったもののように感じるということ。もう1つは在来種と野生麹菌のつながり。これも同じ理由で、菌がどういったものを好むかといえば、より長くその土地に馴染んでいったもののようだということ。それが、わくさんが日々の菌とのかかわりで感じていたことでした。そしてその菌の好みは人が食べておいしいかどうかとは関係がないようだ、とも。
わたしは米農家としてこれまで10品種以上の稲を育ててきました。その多くが在来種とよばれる明治時代ごろの品種です。正直にいえば、食べておいしいと思えるものは多くありませんでした。素朴であると表現することができるかもしれませんが、粒は小さく、味はあっさりというよりたんぱくです。米農家が育てる品種を選ぶときの基準は主に2つで、おいしいか?そしてたくさんとれるか?ですが、わくさんの話を聞いて思ったのは、そこに第3の基準があるのではないかということです。つまり菌が好み、おいしいお味噌に醸してくれるかどうかです。
規模の割合でいえば、日本の田んぼから在来種は消えたといって差し支えないといった記述をどこかの本で読んだことがあります。それがまた、もしわたしたちの試みが本当なら、昔はよかったという懐古主義ではなく、今わたしたちが食べても新しくおいしいものとして見出される稲があるかもしれない。そんな考えに至って以来、小さな米農家ではありますが、ささやかな使命感のようなものを抱いています。
そしてそんな在来種の中には、穂先の毛である芒のあるものもたびたびありました。黄金色に染まる秋の田んぼの一隅にそうした在来種の白や黒がよく映える、そんな不思議で美しい風景を初めて見たときのことを今でもよく覚えています。米をつくるために育てている稲の、そのものの立ち姿をただずっと見ていたいとすら思いました。それから自分のなかで、「はじまりの味噌」は目的のようでありながら同時に、在来種を育てつづけていく手段であるかのような感覚があります。
ちょうど時を同じくして前述の本に出会いました。色彩豊かな田んぼをほんのわずかでも想像できた自分がそこで思ったのは、それを見てみたかったということでした。かつての田んぼは今のような機械農業に適した四角ばかりではなく、もっとさまざまな形をしていました。よりそれぞれの地形に沿ったものだといってよいと思います。そこで育てる稲には早稲から晩稲までがあり、籾も芒の色もさまざまで、畔には大豆や稗を植えていた。今よりも田はもっと身近で、そしてある種の強い覚悟をもって向き合っていたであろう色彩豊かな田んぼとその美しさを、わたしは見てみたかったのです。
もちろんいまの黄金色の農村風景も美しく満ち満ちています。一米農家としてそれを実現するための努力や苦労もすこしはわかってきたような気がしています。しかし、それがわたしたちの原風景になったのは明治の中期ごろからです。それ以前に生きた人たちは、もっと多様で色があふれた風景のなかで暮らしていたのです。そんな農民たちにとっての当たり前や価値観は、それだけでも今とはきっとまたぜんぜん違ったものだったのではと想像します。決して楽ではない農の暮らしにあった豊かさと楽しさの深みを、自分はいつか味わえるんだろうかと思います。
農民というものは、朝に霧を払って田に出かけ、夕に星空を見つつ帰路につくものである。また、遠方にゆき、あるいは野山で働いていて、少し休もうとするとき枕にするのは、あぜである。そのような暮らしのなかにこそ楽しみがある。
『耕稼春秋』
この蒜山に移住する前には広島の農村に住んでいました。お借りしていたのは明治時代から続くという大きな古民家で、そこには一枚の古い写真が残っていました。それは昔のその家を撮ったもので、茅葺きの屋根に牛や鶏がいて、周りのいろいろなものが生活の用にそった美しさを抱いているような、そんな写真でした。中でもわたしが一番驚いたのは、今よりもずっと裏山が遠かったことでした。
地元の人たちはみな、昔は山で遊んでいた、ここにもあそこにも山に入る道があった、と言います。それくらい山の資源は生活に密接で重要なものでした。いまでは蔓草に覆われて、藪化して、道という道もなく、倒れた木々がそのままに朽ちているような暗い裏山も、かつては光の入る山だったはずです。それは色彩豊かな田んぼと同じように、自分が見てみたいと思った明るい裏山です。人が関わることのない雄大な自然ではなく、人が自ら手を入れて心地よいと感じるような里山としての自然に、わたしはずっと憧れているんだろうなと思います。
ちょうど9年前の今ごろ、宮古島でパーマカルチャーの講座を受けたことがあります。たくさんのことを学び、正直なところ未だに咀嚼できていないようにも感じていますが、心に深く残っているお話がひとつあります。それは人間の奥底には死への恐怖と永続への希求のようなものがあるのではないか、そしてそれは自然と深く結びつくことで得られる感覚によって満たされるのではないか、というものでした。会社員を辞めて東京を離れて1年ほどの当時のわたしには難しいお話でしたが、なんだかよくわからないけれど、いま自分はものすごいことを聞いている気がする、そんなことを思っていました。
あれから地方に移住をして農家になって、より自然が身近になりました。四季のめぐりにあわせてそのときどきの営みを粛々と繰り返していると、その日々こそが愛おしい本質のようにも思えてきます。豊作もあれば不作もある、ほとんどの時間をひとりで過ごすのだけれどなぜかさみしくもなく賑やかなようにも感じられる。田んぼという自分が関わった小さな自然のなかで、それが周りの風土にも馴染んだものであればあるほどに、右も左も、上も下も、どこにもない。ただありのままの生をこのまま続けていけたらいいなと思うときにふと、宮古島で聞いたお話が体感的にもわかるような気がすることがあります。
呼吸をする土壁の家で不思議と心が落ち着くように、自然素材の衣類が肌にあうことがあるように、本質的であるがゆえに今でも変わらない合理性を伴った自然との関わり方がもっともっとあるのではないかと思います。
|参考書籍
耕稼春秋(農山漁村文化協会)
江戸日本の転換点(NHK出版)
享保元文諸国物産帳集成 第1巻 郡方産物帳
稲学大成 第3巻 遺伝編(農山漁村文化協会)
江戸時代中期における諸藩の農作物(安田健)
森と田んぼの危機(朝日新聞出版)
自然により近づく農空間づくり(築地書館)

[0]米と稲作の歴史をまっすぐに学んでいく
2024年12月27日
これからは田畑があるから百姓をやるんじゃない。百姓には豊かな才能と努力が必要だ。未来はそういう人間が田畑を耕す。大自然の営みを受け入れる心、土と水の力を理解し育む能力、あらゆる困難に耐え、乗りこえるエネルギー、そしてなによりも農作物への限りない愛情。それらが百姓に課せられた資格だ
漫画『夏子の酒』にて、幻のお米「龍錦」に向き合う農協組合長さんの台詞として描かれる言葉です。背中を押されるような背筋を伸ばされるようなこの言葉が、米農家2年目の冬に初めて読んで以来ずっと心に残っています。
—
わたしは神奈川県の小さな町に生まれました。会社勤めの父と専業主婦の母のもとに育ち、東京の大学を出てそのまま会社勤めをしていました。学生時代から関心のあった国際協力の仕事を志そうと決めて退職し、妻に出会い、農業に出会い、流れのままに移住して米農家になりました。
何代にも渡る農家ではなく先祖代々の土地もなく、農学部の出でもなく地元民ですらない移住者です。いま田んぼに広がる雪が解ければ米をつくりはじめてから7回目の春がきます。何年経ってもこの土地で生まれ育った人たちの身に刻まれたことはわからないままだと感じながらも、それでもなおこの土地らしさをそのままに生き写すような農作物をつくれたらと思ってしまいます。そんなときいつも、自分はちゃんとした農家であれているんだろうかという問いが心に浮かびます。資格のいらない農家の資格を、自分は持っているんだろうかと。
だからこそ自分の選んだ米づくりという営みが何なのか、どこから来ているのかをもっと学びたいと思いました。それも異なる文化や道から稲を見つめるのではなく、米の歴史、稲作の歴史をまっすぐに深く広く知りたいと。ゆくゆくは自分がこれからどうしていくべきか、どんな言葉を発していくべきか、すこしでも明らかになっていったらと願っています。そのために今はまず、日々田んぼで感じること考えることをもって、一冊一冊を身体で読んでいきたいと思います。