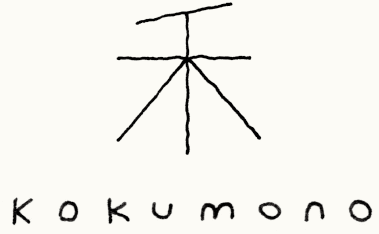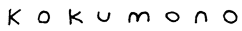ようやく、3.11を想う
2025年03月14日
2011年3月11 日の東日本大震災から14年が経った。
今まではこの日に何かを想う、ということは全然できていなくて、ただの日常として過ぎ去っていた。
でも、なんだか今年は違う。湯梨浜町のジグシアターで「東北記録映画三部作」が上映されていて、それがどうしても気になっていた。自分のスケジュールと映画のスケジュールをにらめっこしながら、上映時間をひとつずつ確認するものの、どうしても行けそうな日が見つからない。鶏の世話、たまごの発送、餌の仕込みなどの日々のルーティンが張りめぐされ、それをサンドイッチする子どもたちの送り迎え。いまの私の日常に、映画が入る隙がなかった。
そんな気持ちで迎えた、2025年3月11日。
ふとパソコン画面を眺めながら、東北の映画やっているんだね、と夫が声をかけてきた。そんなことは知っている。私は行けないけど、夫はいけるのでは?と勧めてみたら、一人じゃなんか嫌だなという。私は一人でも行きたいけどいけないのにと話しながら、この時間行けるんじゃない?というのを見つけた。夫に夕方の鶏の世話と子供たちの迎えを託し、15時からの上映へと足を向けた。
その時間の作品は「なみのこえ新地町」。福島県新地町の人々が当時の様子を話す、という内容だった。夫婦や職場の同僚、友人、親子の会話だったり、スタッフが聞いていたりする会話を映していた。ただそれだけだった。
それだけなのに、思わずぐっと涙が出そうになる瞬間が何度もあった。新地町には全く馴染みがなかったのだけど南相馬市に近いということもわかった。そういえば、南相馬市に行ったことがあったのを思い出した。
映画を通して、思いがけず私の2011年3月11日、そしてその後のことを思い出した。
大学3年生が終わるころで、就職活動が本格的に始まりつつある時だった。東京の三鷹市で一人暮らしをしているアパートで迎えたその時。揺れの強さにびっくりし、とりあえず家の外へ出てみた。通りにはそんな人たちがちらほらいた。なぜか、みんな空を見ていた。少しして揺れがおさまって家の中に戻り、テレビをつける。そこから、少しずつあの悲惨な映像や情報、鳴り響く警戒音が続いた。
なんとなく心細くなり、いつもお世話になっている、大学の卒業生夫婦の家へ行った。そして、そこに、その夫婦のお父さんがいた。普段は石巻市に住んでいるのだが、たまたま東京に用事があって、そこにいた。けれどもお母さんは石巻にいるという。夫婦はこれからお父さんと石巻へ向かうため荷物の準備をしていた。手持ち無沙汰な私とお父さんは、なんとなく世間話をしていた。こんなに大変な時なのに、私たちはそうして時間を潰すしかなかった。災害を回避したという意味では、きっと幸運なお父さんだった。でも気持ちは渦中にあって、心細そうで静かで不思議と穏やかに話すその姿をなんだか今でも覚えている。そして、渦中の石巻市に帰っていった。
そうして、その瞬間が過ぎていき、大きな企業の就職活動は軒並み延期。手帳の予定がすっかり空いた。少しずつ状況が落ち着いてくると、建物に損壊があったアジア学院の片付けの手伝いや、学生ボランティアで瓦礫撤去の手伝い、砂浜のゴミ拾いなどに参加した。有機農業をする人たちとの関わりもあったので、放射能汚染についての勉強会などもよくあった。少し年上の友人たちがやっている物資支援活動の事務仕事なども引き受けた。学園祭であえて福島市の有機野菜を使ったスープを売った。就活は、スケジュールに遅れが出ず早々に内定が出た生協に決めた。自分ごとにあまり時間を使いたくなかった。そうして、大学4年生は卒論と震災支援に関わる活動という日々だった。
ただ、そんな活動も就職してから途端に何もできなくなった。社会人1年目のストレスはなかなかなもので、平日は帰って寝るだけ、土日は体力回復のために寝るだけ。友人との活動も参加できないし、いつしか遠ざかっていった。
そうして、薄れていったいろんなことが映画を観ながら急に蘇ってきた。
自分の生活にいっぱいいっぱいだった期間を過ぎ、子どもが産まれて子どもの世話でいっぱいいっぱいだった日々が過ぎ、14年も経っていた。気づけば地理的にも遠く離れ、ああこの間、何もできなかったな、と思った。
夫は、震災直後に社会人1年目になった。その時何もできなかった、ボランティアなどにも行けなかった、という心残りがあるという。だから当時の話を誰かと共有することに引け目があるようだった。
今住む地域の人は、被災地から遠く離れていて、あまり当時の思い出などはないのかなと思っていた。ふとご近所の人とそんな話題になった時、その日はまだ小さな子どもと温泉に行っていて、温泉のテレビであの映像を見た、私はこんなところでぬくぬくしているのに、こんなことが今起こっているの?という気持ちだったという話をしてくれた。
きっと私も社会人一年目だったら夫と同じ後悔をすると思う。きっと私も小さな子供がいたら、その日常との対比に苦しんでしまうと思う。
それぞれがその瞬間のことを覚えている。14年経っても、心のどこかに残っている。それなのに、誰もが自分は渦中にいなかった、と思っているような気がする。でも、その時感じたことがある、というだけできっと誰もが当事者なのだと思う。ただ、当事者である以上、それは傷にもトラウマにも後悔にもなる。
そろそろ、その傷を自分もまた負っているのだ、ということを受け入れても良いのではないかと思ってきた。そう思って、私はここに書いてみた。過去を変えることはできないけど、その過去を捉え直すことはできる。あの時の私はきっと傷ついていた。平気なふりをしながら渦中の人のために、と行動していたけれども、きっとそれは自分のためだった。その傷はまだ癒えていないし、向き合うと辛くなる。なんだか真面目すぎるとも思うけど、これからは、そんな気持ちを再確認してあげる日にできるかもしれない、3.11を。
近藤温子

独立5年目を終えて
2024年01月31日
禾は2019年の3月に独立をしたので、今ちょうど5年目を終えるところです。私にとってここは大きな節目だったので、いろいろなことを振り返りながらすこし書いてみます。
5年目が区切りというのは、一つには補助金のことです。私たち、というか正確には個人事業主なので私は、認定新規就農者として補助金を毎年頂いています。それがこの5年間でした。年に2回いろいろな報告書をつくって、市役所での面談と田畑での現地面談をすること、それもひとつのルーティンでした。
(先日ちょうど10回目の面談があって、これで終わりかぁと思っていたのですが、補助金給付終了後も簡素化された報告と面談はあともう5年続くと聞いて驚きました…!)
5年前を振り返ると、それまでの私はずっと会社やNPO法人に雇われていた身だったので、農家になること以前に独立すること自体が怖かったのをよく覚えています。自分の身一つでものをつくって売って生計を立てる、何でもないような自分がそんなことを続けられるのかなと不安でした。独立人?の大先輩であるイラストレーターのアラタ・クールハンドさんが「雇われるっていうのは点滴に繋がれているようなものだから。抜くときはそりゃ怖いけど、でもそれ無しで生きられることはいいことだよね」と言っていたのを何度も思い返しました。
ちょうど同じ年には息子が産まれました。尊くて愛おしい、人生で一番大きな変化だったかもしれません。今だからもう書けますが、家族3人を自分ひとりでどうにかしなきゃと気負いながらも、独立したてということもありすべてがままならなくて、心を病んでいた時期もありました。そういうときに意外とあっけらかんとする妻にも救われました。
それから思い出すのは、お米の販売初日のこと。これは会う人会う人に妻が楽しそうに話しているおもしろネタですが、いっっっぱい注文がくるんじゃないかと思っていたのです…!なぜなら私の研修先では販売開始日にはすごいことになっていたので。だから、たくさん来る注文に応えていけるのかなって心配しながら公開ボタンを押して、でも日中何もなくて落ち込んでいたら、夜中11時過ぎに1件だけ大学の友人が買ってくれたんです。陰ながら応援してたよと言ってくれて。それから数ヶ月かけてお米は売り切れたのですが、きっと一生忘れない1件です。
前置きのつもりで書いていたものが長くなりましたが、今回一番書きたかったのは感謝の気持ちとお礼の言葉です。誰よりもまずは研修で約1年間お世話になった蒜山耕藝のゆうじさんとえりかさん。おふたりの活動がどれだけすごいのか、同じ農家という立場になってみてその思いは年々強くなります。技術的にはきっと教わったことの半分もできていませんが、農家としての心構えや姿勢のようなものはずっと心の真ん中に置いているつもりです。そして同じ農家としていえば、広島・宮島の中岡農園の悟史さんと千内さん。野菜とお米の物々交換はもちろん、毎年冬に一度だけお会いするたびにドーン!と大きな愛を頂いて、その勢いで春から秋までがんばれているような気がします。
それから市役所や農政局の方々、土地を貸してくださってる地主さんや地域の方々、農作業を手伝ってくれたり一緒にものづくりをしている友人たち、禾の農作物や加工品を扱ってくれているお店の方々、そして一緒に食べてくださっているみなさんに。それから、初めて農に触れるきっかけをくれたアジア学院のスタッフ、ボランティアやアジア・アフリカの農村に暮らす友人たちに、パーマカルチャーセンターの設楽さんと仲間たちに、ここに移り住むまえに妻と暮らしていた広島の甲奴町のみなさんに。と、どこまでも遡ってしまいそうなのでこの辺で。
自分たちがどれだけまわりの人たちに助けられているのか、そういうことがはっきりと目に見えてわかるようになる。それが独立するということなんだと思います。こう見えても根が真面目な私はできなかったことばかりを気にかけてしまいますが、私たちのような何も持たない普通の人が見知らぬ土地に移り住んで、この時代に2人の子どもを育てながら5年間も農家として続けてこれたこと。それ自体がすごいことなんだと思います。そんな感謝の気持ちを改めて言葉に残しておきたい節目でした。いつも言っていますが、いつも本当にありがとうございます。
せっかくだから、これからのこともすこしだけ
この5年間は独立前につくった計画書を見ながらの5年間でもありました。それは一つの道標としてずっと心のなかにあって、お金のこともあるから当然ではありますが、そこからは大きく変えにくいなぁという心のバリアみたいなものもありました。だからこれからのことを思うと、なんというか、開放というと大げさですが良くも悪くももっと自由だなぁと感じています。(実際には、今度は認定農業者に向けた計画書をつくるのですが、それはさておき…)。
畑のあり方を来年から大きく変えてみようとしているのも、こういうタイミングで考えられることが広がったからでもあります。東北で研究されていた立毛間栽培というもので、これができるようになったら今まで畑を3分割して毎年大豆と麦を収穫していたものが、1つでよくなります。今までの管理も不十分でしたが、もっともっと精度の高い管理が求められます。きっと毎年いろいろな失敗をするんだろうなと思いつつ、また何年もかけて技術を磨いていきたいです。
他にも新しく始めてみたいことはいろいろあって、次の春から始まる6年目は、もう一度ほんとうの意味で独立していくんだという気がしています。そして今回は、あのときのような怖さはあまりなくて、楽しみだなぁという気持ちのほうがずっと大きいです。もちろん周りのみなさまのおかげです。自然栽培の穀物と平飼い養鶏、そこが真ん中にあることはきっと変わりませんが、自分たちの生活や田畑との心地よい関わりを大切にしながら、無理なく続けられる形を模索しつづけていくんだと思います。
最後に、最近の自分は内向きになってきたなぁとよく思います。うすうす滲み出てはいそうですが、妻も私もそれほどオープンでウェルカムな性格ではありません。日常は子どもたちとわちゃわちゃして、田畑と鶏小屋を行き来するだけです。数年前から、なんという名前かはわからないけれど、自分たちは人生における一つのピークの最中にいるんだという感覚があります。だから大切なものごとに順番をつけて、それ以外のことを諦めたり、辞めたり、断ったりしています。それは正直いいことばかりではありませんが、自分はそれほど器用でもなければ心身が頑丈でないこともあり、もうこれでやれることをやるしかないんだと受け入れることにしています。歳を重ねると先が見えてくるみたいなことは、どうも良くはないことだと思っていた気がしますが、実際にはそうではないなと思いました。定まるリズムがあるからこそ、その中での工夫や喜びもあるし、そこからつくられる新しいものもあるように思います。
子どもたちに健やかな日々を送ってもらうこと、そばにいること。私たちがいいと思えるあり方で農業を続けていくこと。それ以外のことはもうほどほどに多くを望まず、そのために励んでいけたらと思います。

宮島の自然が育てる野菜と物語
2023年03月17日
先日、広島の宮島で中岡農園を営む山本ファミリー(悟史さん、千内さん、千草ちゃん)が遊びに来てくれました。山本さんの宮島野菜と、禾のお米・卵を物々交換をしていて、毎春宮島にいったり蒜山に来ていただいています。写真は昨春の宮島。美しい桜と、山本家にすっかり溶け込んでいた息子が印象的でした。
本来は一泊していただく予定が、私が風邪の病み上がりでやむなく日帰りでの滞在になりました。いつもより短い時間に私はボーッとする瞬間も多く、なんでこんなときに…!と残念でなりませんでしたが、それでも思い出深いことがたくさんあったので、書き残したいと思いました。
——
昨年の夏。一羽の鶏が卵を温めているのを妻が見つけて、どうなるんだろうと実験的に見守っていたところ6羽の雛が産まれました。1年ぶりの雛たちは本当にかわいくて家族みんなで大はしゃぎでした。ただ我が家の養鶏サイクルでは難しいこともあり、前々から鶏を飼いたいとお話されていた山本家に引き取っていただきました。2週間の短い夏の思い出でした。
あれから半年が経ち、我が家では鶏をみんな絞めて、たくさん残しておいた卵もちょうど無くなった頃、宮島に移り住んだ鶏たちは産卵をはじめていました。山本さんが持ってきてくれたその卵を見たとき、すごく不思議な気持ちになりました。終わったはずの命が、自分たちには見えていなかったところで続いていて、なんというか命の境界線の曖昧さみたいなものを感じました。はじめましてとおかえりを一緒に言いたくなりました。
そしてもう一つ。数年前、山本さんがお客さんに禾のお米をおすそ分けしてくれていました。その方はそのお米をすごく気に入ってくれて、それから産まれたお子さんの名前に「禾」の字をつかってくださったそうです。「私たちも最近それを知ったんよ〜」と笑顔で教えてもらったとき、私はちょっと言葉に詰まりました。うれしい気持ちと畏れ多いような気持ちになって、どう答えたらいいのかわからなくなりました。
それから数日間このことを考えていて思ったことがあります。私は、自分なんてほんとにまだまだなんです、という表現をよく口にしていました。謙虚とかではなくて実際にそう感じるし、周りから見ても実際そうだと思うんです。でも、そういうのはもうやめなきゃいけないような気がしました。現実がどうあれせめて姿勢だけでも、背筋を伸ばして凛としていなきゃいけない。いつか会えたときその子に恥ずかしくない農家でありたいと思ったことを、こうして書き残しておきます。
——
2年前につくった冊子『ぼくたちは夏に味噌をつくる』にも記した通り、藤原みそこうじ店さんと始めた「はじまりの味噌」という取り組みも、そのきっかけは山本さんでした。農家としても人としても私から見れば大先輩ですが、いつもいつも、あっちゃんはすごい、りょうくんはすごい、と私たちの存在をまるっと包み込んで背中を押してくれます。一緒に過ごせる時間は短くても、節目節目でたくさんの小さな感動を共有している家族のような感覚があります。また来年会えるのを楽しみに、一年のはじまりを告げる春の一日でした。
そんな大好きな中岡農園さんが最近また野菜の定期便枠を募集されるそうです。ぜひご覧になってくださいね。