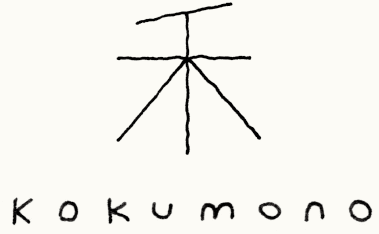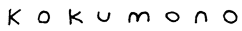お米の価格改定について
2025年08月19日
今回はお米の販売についてお知らせです。今秋収穫をするお米(うるち米のササニシキと亀の尾)から、価格を上げさせていただこうと思っています。
|玄米800円/kg→900円/kg
|白米900円/kg→1,000円/kg
ご負担を増やしてしまい申し訳ありません。ご家庭にあわせて、お買い求めいただく量や頻度を見直していただくなども含めてご検討いただければ幸いです。あまり直前でのお知らせではそうしたことも難しくなってしまうかと思い、すこし先のことではありますが早めにお知らせをとこのタイミングで書かせていただきました。
—
この価格変更について長いあいだずっと悩んでいました。それが必要だと感じてしまうのは物価が上がり生活によりお金がかかったり、どうしても必要になる諸経費も毎年のように上がったりしているからです。そしてできればしたくないと思うのは、やはり食べていただく方へのご負担が増してしまうためです。
みなさんご存知のように、ここ最近の米価高騰以前にはわたしたちのお米は一般的なお米よりも高い価格でした。それは一般的な栽培方法に比べて基本的には収穫量が少なく、また作業量が多くなるため管理できる田んぼも増やしにくいためです(もちろん人によりけりですが、概ねそうした傾向にあるとは言っていいと考えています)。しかしそれをもってして、お前の米は都市にいる金持ち相手の商売だな、といった趣旨のことを幾度となく言われたことがあります。
そんな風に思われているんだ!という驚きと困惑で、初めのうちは何と返せばいいのかもわかりませんでした。ほとんどの場合では批判と揶揄と冗談が入り混じったようなトーンで、たわいもない会話のなかにスッと入ってくるので、そういうときのわたしはだいたいすぐには反応できず尾を引くようなモヤモヤをずっと抱えてしまいます。それでも何度か経験するうちに、心の準備もできるようになって、そういうわけではないと思っていますよとお話できるようになりました。
収入の多寡がそうであるのと同じようにお金の使い道も人それぞれです。家につかう、身につけるものにつかう、好きなものや趣味につかう、自分の学びや子どもの教育につかう、ほんとうにさまざまです。お金は手にするときもつかうときも、きっとその人らしさみたいなものがよく現れるのだと思います。
わたしたちのお米はたしかに高価であるものの、お金が余って余って仕方ありませんみたいな特別な人ではなく、食や農に対してより強い興味関心をお持ちなだけの、ふつうに働くふつうの人たちがそれぞれの理由でそれぞれに限られた生活費のなかから選んでくださっているのだと思っています。それはわたしたち自身もそうだからです。
わが家も、お米や卵など自分たちでつくっているものを除けばふつうの家庭です。穀物は農作物の収穫量がずっと不安定で、豊作の年には落ち着くけれど不作の年には一気に苦しくなるし、養鶏は子どもたちとの関係でそもそもできる年もあればできない年もあります。農家になってから、例えば貯蓄ができるほどの余裕を持てたこともありません。家は格安でお借りしているし、ほぼすべての農機具は中古をなおしなおしつかっています。
そんななかでも、食べるものに関しては特別な意識を持っています。野菜、お味噌やお醤油、お豆腐にパンに珈琲などなど、この人がつくってくれたものを食べていたいと思うものがあります。品物の安さには心から感謝をしつつも、そうではない理由で選べるものを少しずつでも選んでいくこと、それはいい生活だなと感じています。
それなのに、ただ自分たちのためにと価格を上げて、まわりの方々のご負担を増やしてしまうことを心苦しく思います。その一方で、誰かが価格を上げるという話を見るときに困ったなとか嫌だなとか、そういうことを思ったことがありませんでした。みなさん悩みに悩んだ末に、もう仕方ないという判断で値上げの決断をしている姿を見てきたからです。だからこそ自分もむしろ積極的に、値上げいいですね、これからもつくってください。という気持ちが湧くほどでした。
わたしたち禾の活動も同じように思っていただけるのか、それはわかりませんが、これからもこの営みを安定して続けていくためにどうぞご理解をいただければ幸いです。
写真は、自分たちの田んぼに入る川の水がどこからきているんだろうねと、息子と一緒に山に分け入ったときのもの。軽トラックで行けるところまで行って、そこから更に奥深く30分ほど道なき道を歩いた先に、空がぽっかりとあいて光が差し込むすこし開けたところがあります。そこは澄んだ水がちょろちょろと地面から湧き出てくる、川の出発点のひとつになっています。凛とした空気が流れているわたしの好きな場所です。

いい苗と減点方式の米づくり
2025年07月02日
今年も無事に田植えが終わりました。あぁ、よかったなぁと安堵する一方で、育苗については反省と学びの多い年でした。田んぼの状況も、自分の気持ちも日々移ろってしまうので、今をちゃんと切り取って残しておきたいと思います。
まず、その失敗。またまた芽が出なかったのです。これはわたしにはたびたびある課題で、ほんとうに苦しかった一昨年を50とすると、けっこうよかった昨年は90、今年は60くらいかなぁという感覚です。
毎年、春になるとその年の作付計画を立てます。どの田んぼでどの品種のお米を育てるか、それから品種ごとの面積を計算して、植える間隔を考えて、その田んぼを埋めるために必要な苗箱の数とそれに必要な種の量を出します。それを元にして、種の準備をして種まきをして、育苗をしていきます。といっても完全にゼロからやっていますという話ではありません。例えば今年は昨年と同じにしようと決めたので、昨年のノートを読み返しながら頭のなかでいろいろなシミュレーションをしてみて、1時間もあれば終わりです。
ちなみに、育苗をする苗箱は余剰分をつくります。失敗に備えるのと補植用にと、それなりに多くつくります。ただし、つくったり片付けたりも手間だし苗代の面積も必要になるので、いくらでも多めにというわけにもいかず、経験則的にまぁこれくらいかなという数を狙います。品種にもよりますが、いまのところは3〜4割増しで用意しています。それでもぜんぜん足りなかったのが今年でした。作付面積を減らしつつ、欠株だらけの苗箱だったので補植をかなりがんばって、どうにかこうにかできる限り田んぼを整えることができました。
昨年は比較的うまくいっていたのに今年失敗した理由は、苗代をガラッとつくりかえたからでした。
禾で育てているお米の品種はほとんどがササニシキ、すこしの亀の尾とこがねもち、そして藤原みそこうじ店さんとつくる夏のお味噌用につかう実験的な在来種です。その在来種は年によって変わりますが、基本的にはとても少量です。そしてわたしは、この地域にしてはありがたいことに大きめの田んぼが多く、この少量品種にあう小さな田んぼがありません。それで1枚の田んぼを縦に割って、川下にはこの品種、川上にはこの品種と分けて育てていました。ただ、あまり気持ちよくはありません。生育が違うのに早いほうにあわせて中干しをする必要があったり、収穫作業でも田んぼをグイグイ荒らしてしまったり、やっぱり1枚の田んぼで1品種にしたいなとずっと思っていました。
この課題がついに今年は解決できそうだと思ったのです。それが苗代でした。もともと1枚の小さな田んぼを2つに分けて、片方を育苗する苗代に、もう片方を水路から入る冷たい水を温める温水田としてつかっています。これまでの苗代は苗箱を片付けたあとに緑肥としてエンバクを育てていたので水を入れていませんでしたが、昨年からは緑肥として稲を育てています。苗代のほうに水を入れるので、温水田のほうでも稲を育てられるようになったのです。これに気がついたとき、ついに数年頭を悩ませていたパズルが解けた!みたいなうれしい感覚になりました。
それで、今年は苗代を一から作り直しました。2つに分けてある苗代と温水田のどちらにも秋まで機械が入っていけるようにと通り道をつくり、その分だけ畝が短くなるからと畝を1つ増やし、そのためには中畔を壊して新しくつくり。毎年バタバタする春をいつもよりバタバタさせながら、どうにかこうにかこんなもんだろうと仕上げた気になっていたのですが、うまくいきませんでした。
わたしの観察によると、芽が出ない基本的な理由は水不足です。苗箱と畝の接地がうまくいっておらず水を吸い上げないこと、そしてその畝が他よりも高くなっていて水があまりあたっていないこと、これらが重なると起きる問題のようです。特に前者については土が固く締まってしまうことが多々あって、例えばエンバク緑肥を初めてやった一昨年もこれが原因だったのかなと考えています。今年もその反省を活かしながら仕上げたつもりでしたが、いろいろな面で甘かったのだと思います。
それを踏まえて、こがねもちだけ種まきをやり直すことにしました。芽がきちんと出揃っている苗箱がひとつも無いほどにボロボロだったからです。ここまできたらダメで元々!という気持ちもあったので、こうやったらどうなるんだろうと気になっていた段取りで仕上げてみたのです。(ここからは細かいことで、かつ擬音ばかりの感覚的な話になります…!)。例年、ざっくりと畝をつくったあとに、草を集めて取り除いて、その後は水を入れて水平を見ながらレーキで土を引っ張って高低差をできるだけなくしていきます。それから苗箱を置く直前にはクイックレベラーという機械をつかって、土の表面を振動させてさらに平らかつトロトロに仕上げます。ただレベラーの前がレーキをかけたままだと、場所によっては土が締まっているところがあったのです。それは表面の土だけが水と混ざっていて、もう少し深いところまでは水が入っていないようなところでもあります。それで今回は、レーキのあとに鍬でザクザクとしてそこそこの深さまで土がゴロゴロッとして、かつ水と混じって泥になっている。そんな状態でレベラーをかけると、なんだかいつもよりもすごいトロトロになりました。ザクザクで土がすこし動いて高低差が出てしまったところがあったので、そこは来年への課題ですが、上から鎮圧するまでもなく苗箱を置くだけでちょっとめり込むほどになりました。
そうして育ったこがねもちがなんだかすごかったのです。芽が出揃ったのはもちろんですが、まず違うなと思ったのは色です。ずっと緑でした。禾の苗は基本的には黄色っぽい感じで、田んぼに植わってしばらくするとだんだん緑になっていく、と見えていました。それが芽が出たそばから緑で、その後もずっと緑。こんな苗は初めてでした。これまでも種まきから時間が経って田植え直前ごろにもなるとドドンと立派になる苗が緑になっていましたが、発芽直後からずっと緑でいるのは初めてでした。
それから生育速度。他よりも2週間遅れで5月中旬ごろに種まきをしたので、それだけ田植えもずれるかなと思っていたのです。5月初旬から気温がグッと上がってくるので、まるまる2週間遅れということもないかなとは期待していましたが、6月にもなるともう他を追い抜きそうな勢いがって、早く田植えしてあげなきゃ!と焦るほどでした。
それから苗の大きさ。先に書いたような田植え直前ごろにもなるとたまに見る立派な苗、そういうものは葉先が垂れてきます。それ以外の多くの苗は葉先が上にピンとしていて、田植えからすこし時間が経つと大きくなって少し垂れてきます。このこがねもちは、それなりに多くの苗がそのように葉先が垂れていました。わたしの米づくりは機械作業なので、どうしても苗箱という狭い空間で種を育てていくことになります。それなのに、総じてこのこがねもちについては、まるで初めから田んぼに植えられているかのように育苗ができた感覚になりました。
正直なことを言うと、これまでずっと「いい苗」というものがよくわかっていませんでした。そもそも農業では「苗半作」という言葉もあるくらい苗の出来を重視しています。それに米づくりに関わるあらゆる人たちが、今年はいい苗だとか、いまいちだとかそんな話をしています。今年の5月、隣の田んぼのおっちゃんが田植えをしていたときにちょうど通りがかったので、苗がバチッとできてますね〜!とわたしが(特に何も考えず適当に)声をかけると、いやいや今年はいけんわ〜と言っていました。あ、そうなんだ!(ぜんっぜんわからん…)と思っていました。
わたしの場合、そもそも発芽が課題になりがちだったので、ちゃんと芽が出てくれればそれだけでうれしい苗ありがたい苗、と思っていました。それに、いい苗を大きさというのなら時間をかければ大きくはなっていくので待てばいいだけです。大きくなっていく速さといっても、毎年種まきの日も違うし気温や天気も違うので精緻な比較もできずいまいちピンとこない、と。とにかく自分のなかに、いい苗とか目指すべき苗のようなイメージがまったくありませんでした。それが今回のこがねもちを見て初めて、あぁ、いい苗ってこういうことなのかもしれないと思いました。みなさんに伝わるかわかりませんが、けっこうな感動を抱いています。
もちろんそれで秋の結果がどうなるかはわかりませんが、とてもとても大きな発見でした。そんな発見をする前の、育苗が失敗しているとだけ思っていたときはほんとうにずっと苦しかったし、毎日毎日あーあー言っていて、隣でそれを聞かされる妻も大変だったと思います。それでもうまくいっているときには見えてこない何かが失敗からは見やすくて、きっと米づくりの収穫とは2つあるんだと思いました。たくさんの実りか、たくさんの学びか。いつかそんな気持ちで臨めるようになったら(わたしはまだまだその渦中にはできませんが)、もうどうなっても大丈夫ですね。
それから最後にもうひとつだけ。これまでわたしは人生を加点方式で捉えてきました。自分がやったこと、あったこと、それらが差異をつくっていくのだし、そこに意味が付与されていく、そんな風に考えていました。しかし今回、自分が育てる苗ってこんな姿になるんだと驚きながら、ふと先輩農家さんから聞いて大切にしていたお話を思い出しました。そしてこれは減点方式に近い考え方だったのかなと気がついたのです。
曰く、春から秋まで米づくりにはたくさんの作業工程がある。それら一つひとつを例えば100点でやっていけたとする。そうすると秋には100点のお米ができる。逆にそれぞれで、ほんのささやかでも小さなミスをする。90点だとする。それ自体は小さなものだけど、それが続いていけば90点×90点×90点…となり、秋には50点とかそこらのお米になってしまうんだよ、と。もちろん米づくりは自然と人との共同作業。人の関わり方ではどうにもならないこともあるし、その一方で失敗と思いきやよくできていることなんてこともあります。だからあくまでつくり手や技術者としての心持ちとして、長い米づくりの一つひとつをどれもほんとうに大切しないといけないよ、といった趣旨の話だったと理解しています。
どう見るか次第だと思うのでどちらでもいいのかもしれませんが、個人的にこれはこれでけっこう好きですんなりと受け入れることができました。なぜなら、それは種のポテンシャルをとても大切にしているように思えるからです。種を真ん中に置いて、ほんとうはもっと素晴らしいものになりうるんだ、種にはそんな力があるんだ、そんな強い信念のようなものがこの考えの通底には流れています。だからきっと好きなんだと思います。いつだって種がなりたいと思う姿になっていけるように、そんな気持ちをこれからも忘れずにいたいです。
というわけで、今年つくり手としてはもうとても大きな学びを得ました。それでちょっともう満足してしまっているというか、お腹いっぱいというか。そんな気持ちもあります。わたしはそれほど器の大きな人間ではないので、これ以上たくさんあっても消化できないんじゃないかなと思っています。
ただ、お米もやっぱりいただきたいので秋までがんばります。この夏の過ごし方も昨年の観察や結果も踏まえてちょっとずつ変えています。それがいいことなのかそうではないのか、それはわかりません。それでも結局これしかできないのだとも思います。いいことかそうではないことかよくわからないことを、よくわからないなぁと思いながらそれでも続けていく。そのなかに、たまに、なにかを見つけて自分を変えていく。そんな営みをやっているんだと割り切って、満ち満ちた時間を過ごしていきたいです。

ようやく、3.11を想う
2025年03月14日
2011年3月11 日の東日本大震災から14年が経った。
今まではこの日に何かを想う、ということは全然できていなくて、ただの日常として過ぎ去っていた。
でも、なんだか今年は違う。湯梨浜町のジグシアターで「東北記録映画三部作」が上映されていて、それがどうしても気になっていた。自分のスケジュールと映画のスケジュールをにらめっこしながら、上映時間をひとつずつ確認するものの、どうしても行けそうな日が見つからない。鶏の世話、たまごの発送、餌の仕込みなどの日々のルーティンが張りめぐされ、それをサンドイッチする子どもたちの送り迎え。いまの私の日常に、映画が入る隙がなかった。
そんな気持ちで迎えた、2025年3月11日。
ふとパソコン画面を眺めながら、東北の映画やっているんだね、と夫が声をかけてきた。そんなことは知っている。私は行けないけど、夫はいけるのでは?と勧めてみたら、一人じゃなんか嫌だなという。私は一人でも行きたいけどいけないのにと話しながら、この時間行けるんじゃない?というのを見つけた。夫に夕方の鶏の世話と子供たちの迎えを託し、15時からの上映へと足を向けた。
その時間の作品は「なみのこえ新地町」。福島県新地町の人々が当時の様子を話す、という内容だった。夫婦や職場の同僚、友人、親子の会話だったり、スタッフが聞いていたりする会話を映していた。ただそれだけだった。
それだけなのに、思わずぐっと涙が出そうになる瞬間が何度もあった。新地町には全く馴染みがなかったのだけど南相馬市に近いということもわかった。そういえば、南相馬市に行ったことがあったのを思い出した。
映画を通して、思いがけず私の2011年3月11日、そしてその後のことを思い出した。
大学3年生が終わるころで、就職活動が本格的に始まりつつある時だった。東京の三鷹市で一人暮らしをしているアパートで迎えたその時。揺れの強さにびっくりし、とりあえず家の外へ出てみた。通りにはそんな人たちがちらほらいた。なぜか、みんな空を見ていた。少しして揺れがおさまって家の中に戻り、テレビをつける。そこから、少しずつあの悲惨な映像や情報、鳴り響く警戒音が続いた。
なんとなく心細くなり、いつもお世話になっている、大学の卒業生夫婦の家へ行った。そして、そこに、その夫婦のお父さんがいた。普段は石巻市に住んでいるのだが、たまたま東京に用事があって、そこにいた。けれどもお母さんは石巻にいるという。夫婦はこれからお父さんと石巻へ向かうため荷物の準備をしていた。手持ち無沙汰な私とお父さんは、なんとなく世間話をしていた。こんなに大変な時なのに、私たちはそうして時間を潰すしかなかった。災害を回避したという意味では、きっと幸運なお父さんだった。でも気持ちは渦中にあって、心細そうで静かで不思議と穏やかに話すその姿をなんだか今でも覚えている。そして、渦中の石巻市に帰っていった。
そうして、その瞬間が過ぎていき、大きな企業の就職活動は軒並み延期。手帳の予定がすっかり空いた。少しずつ状況が落ち着いてくると、建物に損壊があったアジア学院の片付けの手伝いや、学生ボランティアで瓦礫撤去の手伝い、砂浜のゴミ拾いなどに参加した。有機農業をする人たちとの関わりもあったので、放射能汚染についての勉強会などもよくあった。少し年上の友人たちがやっている物資支援活動の事務仕事なども引き受けた。学園祭であえて福島市の有機野菜を使ったスープを売った。就活は、スケジュールに遅れが出ず早々に内定が出た生協に決めた。自分ごとにあまり時間を使いたくなかった。そうして、大学4年生は卒論と震災支援に関わる活動という日々だった。
ただ、そんな活動も就職してから途端に何もできなくなった。社会人1年目のストレスはなかなかなもので、平日は帰って寝るだけ、土日は体力回復のために寝るだけ。友人との活動も参加できないし、いつしか遠ざかっていった。
そうして、薄れていったいろんなことが映画を観ながら急に蘇ってきた。
自分の生活にいっぱいいっぱいだった期間を過ぎ、子どもが産まれて子どもの世話でいっぱいいっぱいだった日々が過ぎ、14年も経っていた。気づけば地理的にも遠く離れ、ああこの間、何もできなかったな、と思った。
夫は、震災直後に社会人1年目になった。その時何もできなかった、ボランティアなどにも行けなかった、という心残りがあるという。だから当時の話を誰かと共有することに引け目があるようだった。
今住む地域の人は、被災地から遠く離れていて、あまり当時の思い出などはないのかなと思っていた。ふとご近所の人とそんな話題になった時、その日はまだ小さな子どもと温泉に行っていて、温泉のテレビであの映像を見た、私はこんなところでぬくぬくしているのに、こんなことが今起こっているの?という気持ちだったという話をしてくれた。
きっと私も社会人一年目だったら夫と同じ後悔をすると思う。きっと私も小さな子供がいたら、その日常との対比に苦しんでしまうと思う。
それぞれがその瞬間のことを覚えている。14年経っても、心のどこかに残っている。それなのに、誰もが自分は渦中にいなかった、と思っているような気がする。でも、その時感じたことがある、というだけできっと誰もが当事者なのだと思う。ただ、当事者である以上、それは傷にもトラウマにも後悔にもなる。
そろそろ、その傷を自分もまた負っているのだ、ということを受け入れても良いのではないかと思ってきた。そう思って、私はここに書いてみた。過去を変えることはできないけど、その過去を捉え直すことはできる。あの時の私はきっと傷ついていた。平気なふりをしながら渦中の人のために、と行動していたけれども、きっとそれは自分のためだった。その傷はまだ癒えていないし、向き合うと辛くなる。なんだか真面目すぎるとも思うけど、これからは、そんな気持ちを再確認してあげる日にできるかもしれない、3.11を。
近藤温子