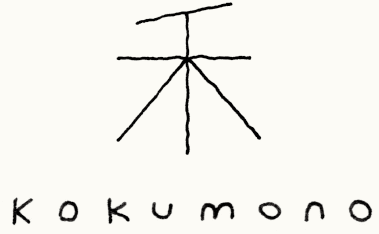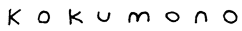2025年のふりかえり|穀物栽培について
2025年12月18日
2025年もあっという間!(ですよね?)今年も栽培のこと、技術的なことをふりかえってみます。昨年同様、農業に関わっていない人でも読めるように意識はしましたが、基本的には自分のメモとして書いています。
|水稲
今年はいつものササニシキ、亀の尾、こがねもちに加えて、鳥取在来種の福山をすこしだけ育てていました。それぞれに課題や発見がありますが、総論としては昨年の豊作に比べたらむずかしい一年だったなという感想です。以前も読み物に書きましたが、まず春の苗づくりを失敗しました。それで植えられる田んぼが減ってしまい、それがまず総量の減少に深く関わっています。
まずササニシキ、こちらは苗が足りずに田んぼが1枚減りました。反収でいえば昨年ほどではないにせよ、これまでのなかでは2番目の良さでした。減ってしまったのは半分の田んぼで草の対応に失敗してしまったからでした。わたしが聞くところによると、自然栽培(無肥料?)あるあるとして生えてくる草が変化します。一年草のヒエやコナギは徐々に姿を見せなくなり、多年草のオモダカやクログワイが元気になってきます。わたし個人の体験としても、はじめの数年はやはりヒエが目立ち、稲はそこそこなのにヒエが多すぎて全面が倒伏する田んぼもありました。そこから深水管理も上手になったこともあるのか、ヒエはほとんど見ないし気にならないようになりました。コナギが気になる田んぼもありますが、いまはやはりオモダカが中心で、ちょこちょことクログワイが見えてきました。先輩農家さんたちから聞いてきたこと変化が目の前で起きていて、おお!自分もついにオモダカに悩むようになってきたのね、、とちょっと感慨深いです。
と、そんなオモダカの対応に今年はがっつり失敗をしています。多めの代掻きで早めに出てくる草を埋め込んだり、定番の深水管理をしながら除草機をかけたり、それから勢いそこそこの田んぼでは気合いの手除草でいい感じですが、勢いのすごい田んぼではびっしりと生やしてしまいました。7月があと2週間ほど増えてくれたらできそうですがとても現実的ではありません。ここ数年続けてきたやり方ですが、このままではいけないなぁとしみじみ理解してきました。次を真剣に考えていかないといけません。
それから亀の尾。1年目の冬に種を譲っていただき、2年目は種を増やし、3年目から本格栽培という付き合いですが、今年はこの5年間で一番の少なさでした。苗が足りずに田んぼの半分ほどしか植えられていないことが大きな要因ですが、来年は田んぼを替えてみようと思っています。思い入れがあるからと家からすぐの田んぼで育てはじめて、それからも作付や効率性の関係で近くの田んぼをあててきました。毎年ちょっとずつの改善を試みていますが、どうも元気いっぱいには育てられていない気がしています。それでふと、2年目に種を増やしたとき家からすこしだけ離れた田んぼの一角に植えていたのですが、そこでの姿がとても立派で好きになったのを思い出しました。家近くの砂地田んぼとはちがい、そこは真っ黒な土。そこで育てたらどうなるんだろうと、今更ながらにふと思ったのでした。もうすこしいろいろ考えたいのですが、来年はそちらでとも考えています。
そしてこがねもち。育苗に失敗したというかほぼ全滅してしまい、蒔き直しをしなかったら収穫ゼロでした。田植えがちょっと遅かったような気もしますが、とにかく収穫ができてほんとうによかった。。お餅シーズンに入っている今、しみじみと喜びを感じています。いまの禾は、もち米よりもうるち米のほうが圧倒的に足りていないので、こがねもちをどんどん増やそうとは思っていません。平年量を毎年しっかりとれるように安定させていきたいなと思っています。
最後は鳥取在来種の福山。こちらは藤原みそこうじ店さんとの「はじまりの味噌」のために育てたお米です。かなりギリギリ、というか9月の長雨がなかったら危なかったかもというほどの晩稲ですが、実りはたわわにありました。2026年の夏に仕込んでもらい、2027年の夏に食べられるお味噌になる予定です。楽しみですね。
それから全体でいえば、収穫で田んぼを大いに荒らしてしまいました。ここまではやっぱり初めてで大きな反省です。中干しをきびしくしたり、ゆるくしたり、溝切りをしたりやめたり、夏の水管理を毎年の雰囲気と前年の反省で微調整をしていますが、いやはやです。。秋起こしはもちろんできなかったし来年の春がもう心配です。
あとは話が前後するけれど、苗づくり。稲作でする大きな失敗のほとんどはここにあります。ミスのないようにと毎年気を付けてはいますが、どうしても新しい穴には落ちてしまいます。それで来年からは、失敗してもすぐにやり直しができるように、いろいろな余剰を持っておこうと思っています。春はとても忙しいこともあり、すべてがギリギリ足りるほどしか用意をしないのですが、ここに改善の余地があるなぁと思ったのです。正確には、思ってはいたけれど踏ん切りがつかないままだったのですが、さすがにちょっとここはどうにかしないといけないと痛感したのでした。
|大豆
今年も昨年同様、サチユタカと日の丸大豆の2品種です。まだ乾燥選別をお願いしているところなので実際の収穫量はわかっていません。ひとまず現時点での感想としてはですが、栽培段階でも収穫量でもサチユタカはうまくいかず日の丸大豆はとてもよかったというのが総論です。
まず、サチユタカ。昨年の大豊作をイメージしつつ、今年の挑戦は連作と麦との立毛間栽培の2つでした。ただ、春先からやや失敗のスタートでした。ロータリーがけはとにかく浅めが基本なのですが、それが弱くて春草がずっと残ってしまいました。日に日に大きくなっていき、徐々に深くしてももう埋め込めない…。例年の倍くらい数はかけたけど、草が残ったままの播種となりました。数年前にも田んぼで似たような失敗をしていたのに、なかなか懲りません。
それから発芽率の悪さ。これは要因がよくわからないままなのですが、半分も芽が出ませんでした(残らなかった?)。何箇所も土を掘ってみて、鳥や獣に食べられる、機械が詰まっていたのか蒔けていない筋があった、などは確認しましたが、これほど芽がそろわないのは初めてでした。結局やり直しで、2枚のうち1枚は2回播種、もう1枚は3回播種をしました。ロータリーがけの数が多かったので土が細かく乾きすぎたのかもしれないと、雨の直後を狙ってみましたが、すこしはマシになったかな程度で劇的な改善はありませんでした。種子の予備がなかったので、正規品ではなくB品をつかっていてそれも影響しているかもしれません。
生育期間中も、そもそも大豆がいないので草も多くなってしまい、収穫直前の晩秋はひたすら草刈り・草取りでした。ここでかける何十時間の、その数分の一でいいから夏にやっていればそれで終わっていたのにな、と毎年思います。季節に寄り添うといえば聞こえはいいですが、遅れないようにするだけで精一杯、というか遅れまくっているのです。
それから収穫についても。なかなかすべてが熟れず落葉しない株も多々ありました。そもそも蒔き直しの連続で予定よりもかなり遅れていたので心配はしていましたが、2枚のうち3回播種をしたほう(より遅かった)がまだよかったのです。播種が遅いと成長が進まず実がつかず熟れない落葉しない、というイメージがありましたが、今年を見る限りでは、ある程度遅いとダメだけど、かなり遅いと株も小さいから熟れるには熟れる、なのかなぁと。わからないことだらけです。
日の丸大豆。こちらは栽培と収穫のどちらもよかったです。前述のとおり今年は稲の苗が足りませんでした。それで当初は大豆畑の一角で日の丸大豆を育てるつもりでしたが、1枚まるまるをそのまま当てることにしました。
サチユタカ圃場のようにサラサラな畑っぽくなった土とは違って、前年が田んぼで排水対策も特別にはしておらず土もゴロゴロ。サチユタカで芽が出ない問題も既に出ていたので、日の丸大豆もあまりいいことにならないかなと心配でしたが、きれいにビシッと芽がそろいました。それからの草の生育も勢いがなく、週に一回畑をぐるっと歩きながら手で草をちょこちょこととっていくだけで問題なく、草が全くないなかでの土寄せを初めてしました。
それから昨年は地生えになっていたのが、今年は播種時期を遅らせることでそれほど伸びることもなく、倒伏もほぼないままで秋を迎えました。こちらは昨冬、他の地域で日の丸大豆を育てている方に電話でお話を伺って気がついたことで、ほんとうにいいアドバイスを頂いたなぁと思っています。機械の収穫ももちろんできるし、サチユタカと比べても鞘付きが株の上のほうなので歩留まりもよかったです。
ただ最後の難点はやはり選別作業です。おそらく今年も、平べったいその形状から機械での選別がほとんどできないのだと思います。昨年は友人にもお手伝いいただいてのひたすら手作業、のべ100時間ほどかけて製品に仕上げています。今年は倍以上の量がありそうなので、200時間、、?と思うとなかなかです。ここがもう少し良い形になれば日の丸大豆を中心にしていきたいのですが、鞍掛大豆のいい選別方法なにかないかなぁ。。
という感じで、まだまだ課題の多い大豆栽培ですが、やっぱり稲と大豆のローテーションをするかなぁと悩んでいます。大豆の難易度が一気に下がるからです。ただ田んぼは田んぼ、畑は畑、としていきたいという大前提があったので、うーん、、どうするかなぁ。。冬のあいだにじっくり向き合います。
|麦
大豆のあいだに麦を播種をする、立毛間栽培をするんだと意気込んでいましたが何もできませんでした。大豆の草が多くなってしまったことと、大豆と稲のローテーションを考えはじめたのでやめておきました。こうなると、麦は麦でずっと連作をする案もありますが、それをできる圃場がないし、もし圃場が増えたとしてもいまはやはり稲や大豆を育てるべきでは、と感じてしまっています。麦は風景としてもすごく好きなのでどうにか育てたいのですが、どうしたものか、いまは見通しも立っていません。
|小豆
と、ここまで昨年に比べればさみしいばかりの結果でしたが、小豆だけはとてもよかったです!育てたものは2品種で、大納言小豆とヤブツルアズキ。
大納言小豆は家庭菜園をほぼ諦めている我が家には珍しい自宅用で、2年前に初めて育てました。記録によるとそのときは100gほどの収穫だったのが、今年はなんと2.7kg。集落の方にもお裾分けをしつつ、冬のあんこもちが楽しみです。それから藤原みそこうじ店さんに頼まれてはじめたヤブツルアズキ、こちらも過去最高の3.8kgの収穫でした。
まず、栽培がとてもうまくいきました。例年の失敗は草負けです。そもそもヤブツルアズキは地生え気味で除草もしにく、気がつけば手を入れるのも大変になっていて、そのまま諦めて秋を迎える、です。今年は徒長しないよう播種時期を遅らせて、かつ簡単な除草作業をとにかくこまめに行いました。草が見えないうちからレーキで地表をガリガリ削っていくだけ。そもそも生やさない、そしてそのまま株が大きくなっていき手をかけなくてよくなる、という理想的なシーズンでした。この良いイメージをもって来年も臨みたいです。(うれしかったので、写真もヤブツルアズキのものです)
ただ、収穫はまだまだ課題です。どちらも数kgと言いつつ、すべてが手作業なのでなかなか大変です。例えばヤブツルアズキは熟れるタイミングが鞘によってかなり異なっていて、しかも熟れるとすぐに弾けて落ちてしまいます。それで10月初旬から一ヶ月、ほぼ毎週のように鞘ひとつひとつを収穫して乾燥選別をしていきました。歩留まりはよかったものの、のべ5日間ほどかかっていて、もう少し効率的な方法を見つけないとこれ以上は難しそうです。こちらも要検討ですね。
—
こうして文字にするにあたって、昨年と今年の日誌を読み返しました(就農以来ずっと綴っているのです)。すると、ぼんやりと抱いていた総括が実態とは違っていたり、忘れていた当時の反省を思い返したり、なんだかこの営み自体がわたしにとって大切な時間だなと思うようになりました。
先日、友人と夜な夜な電話をしていたときに、書くことがすこし話題になりました。どうして書いているのか、自分にとってはどこまでいっても自分のためなのです。それは、ぼんやりと頭に漂っている考えをひとつひとつ文字にすることで、書いてみたけどそれってほんとう?と自分に再度問いかけたり、ここはなにか大切な気がするからもっと先があるんじゃないの?と思えたり。頭の中にだと止まっている思考が、文字と自分のふたりになることで進んでいくような感覚があるのです(いまもまさに書きながら考えていますしね)。
今年はどうだった?と聞かれると、昨年の豊作に比べればそうでもなかったですね〜、むずかしいです。みたいについつい答えてしまうのですが、グッと深い学びと経験を得ているんだなと思ってきました。来年にはまた来年の土と種がありますが、冬を超えてまた来年の自分になって、春からまた精一杯やっていきたいです。

食べるものへの配慮
2025年11月10日
10月半ばに鶏の一部を廃鶏にしました。昨年の春から飼い始め1年間たまごを産んでくれた鶏たちです。
禾としては実に3年ぶり2回目の廃鶏。処理していただいたのは前回と同じ岡山市の三島食鶏さんです。この時ばかりはちょっとかわいそうなのですが、鶏を入れる専用のカゴに7羽ずつくらい入れて、軽トラに3段積み、高速道路を使って2時間の道のりです。もう少し近くで、または自分たちで捌けたらという思いはありつつ、販売するためには免許を取得した施設でないといけないため現状自分たちではできないし、このような仕事をする会社さんはもうそんなに多くはありませんし、ひとまず県内で良かった、今回も引き受けてくださってありがたいという思いです。朝から夫と一緒に必死にカゴに詰める作業を。3年前は妊婦だったのでほぼ夫が一人で詰めて運んでくれました。今回は身軽なのがこれ幸いで私もしっかり捕まえて、私が岡山市まで運んで屠殺していただきました。空っぽになったカゴを持ち帰り、がらんとした鶏舎を見てふうと一息。命をいただいて生きているという実感をする瞬間です。
そうして、パック詰めされたお肉が我が家に帰ってきました。早速、家族でいただこうと思って食卓に出すと、なんと6歳息子が「たべたくないな〜」と。いつまでもぐずぐずしていたので、はよ食べんさい!と食事を促しても鶏肉には手を出さずにごちそうさましてしまいました。
そんなことが何度か続いたので、よくよく話を聞いてみると、うちの鶏のお肉は食べたくない、他の鶏肉やうちのたまごは大丈夫と思っていることがわかりました。少し目をうるうるさせながらそんなことを話してくれて、彼なりに寂しさと悲しさを感じていること、食べられるものと食べられないものの線引きを考えていること、そんなことがわかってきました。彼としては、たまごは生きていないから食べられる、生きている鶏を殺して食べるのは嫌、それが直接には見えない他の養鶏場の鶏は食べられる、ということなのかなと思います。廃鶏やお肉にして食べることを伝えてても、それまでは特に反応がなくて、今日鶏連れて行ってきたよと言った後には、鶏舎を見に行って少なくなったね!くらいのコメントしかありませんでした。いざ食べるとなった時に、きっときっと彼なりに何度も考えたのでしょう。わたしたち夫婦がそんなことに向き合うようになったのは、彼よりずっと大人になってからです。よく言えばこれがまさに食育です。しかし、本人の意思とは関係なく農家の子として生まれて、幼い頃から命を食べることに向き合う彼の気持ちは一体どれくらい重いものを背負っているのだろう、と少し申し訳なく思いました。
食卓が生産現場から離れているという現代の食事事情を私は悪いことではないとも思っています。男木島・ダモンテ商会さんの「広いキッチン 長いレシピ」という本の中で、二宮将吾さんが、鶏の屠殺から焼き鳥にして食べるまでの過程を体験したのちに「料理とは、食材のポジションに関する情報をデザインするための人間の技術体系」(p.57)であると指摘しています。調理方法によってその生き物の「存在感」を見せたり隠したりしていて、「食べる者への配慮が料理の技術を発達させる」(p.57)と語っていました。これはすごい発見だなと私も思っていて、読んでからずっとその通りだなと感じています。例えば、私自身たまごを食べるときに、ゆで卵は命を感じすぎて食べにくく、スクランブルエッグにしてしまった方がいいと思う時があります。私はたまごを孵化させた経験があるため、スクランブルエッグの方が鶏やひよこの存在感を感じにくくなるからです。
今よりずっと生産現場が近かった頃は、そのような料理の発明が人々の精神を支えてきたこと、生きることへの罪悪感を薄めてきたことがあるのではないかと感じています。食卓と生産が遠いことは何かと問題視されがちですし、私もできるだけ生産の場で起きていること感じていることを伝えたいとは思っています。ただ一方で、その距離感の居心地の良さは人ぞれぞれであり、それぞれ異なった配慮が必要であると息子の想いを知ってより一層感じました。

たまご定期便「まるごとコース」始めます
2025年10月10日
一時休業していた養鶏部門を再開し、たまごの販売を始めて1年が経とうとしています。この間、たまごをご購入いただいた方、定期便をご利用いただいた方、暖かく見守ってくださった方、本当にありがとうございました。多くの方に支えられてまずは1年間たまごをお届けできたことに深く感謝しております。
そして、11月より、新しく「たまご定期便 まるごとコース」を始めます。概要は以下の通りで、まずは現在たまご定期便をご利用の方からご案内とさせていただきます。
頻度|月1回 発送日不定
数量|11月から翌年9月まで:たまご20個か30個、最終回10月:親鶏の肉(内容量未定)
価格|月々2700円(税込)
送料|地域ごとに異なります。今までのたまご20個コースと30個コースの間の送料です。
まずたまごは、鶏一羽が1ヶ月に産む量のたまごをイメージしてお届けしたいと思っています。鶏がたまごを産む量は季節によって変化があります。多くても1日に1個なので30個、少なくなると2日に1個の日も増えて20個くらいになります。そんな季節の変化を反映し、月1回、20個か30個のお届けを予定しています。ざっくりとした予定では、11月から春先までは30個、夏が過ぎて秋に向かう頃には20個になるかなと考えています。また、最終的にたまごを1年も産むと廃鶏となり、お肉となってその命をまっとうします。このお肉を年1回お届けを予定しています。こうして、たまごもお肉も含めて、まるっと鶏たちの生き様をお届けするという内容です。
基本的には、お届けのタイミングも、個数も、セット内容もお任せのまるごとコース。受け取り手にとっては、きっと不便なこともあるかと思います。それでも、鶏たちのリズムを想像できるような、自然の一部を垣間見えるような、そんな体験がお届けできたらいいなと思い、始めてみることにしました。
一方で、お届け曜日や内容についてのご希望は、できる限りお受けしたいと考えています。例えば、着日は土日がいいや平日がいい、月の前半や後半がいい、お肉はちょっと苦手なのでお肉の月もたまごがいい、などなど。あくまでみなさまの日々の暮らしに寄り添いつつ、たまごやお肉のお届けができたらと考えています。
————————
「まるごとコース」を始めるにあたっての経緯についてつらつらと書いてみました。
休業中に鶏舎を広くしたこともあり、休業前よりも多くの鶏を迎えての再出発でした。たまごを産み始めた昨年秋は、日々たくさん産まれるたまごに販売が追いつかず、たまごが余り気味になることも多々あり、心優しい方々にたくさん助けていただきました。再開といえども、1年目と同じように販売に苦しんだ期間を支えてくださった方々に、感謝をしてもしきれない思いでいっぱいです。気づけば多くの定期購入の方に支えられ、あくせくせずともたまごをきちんとお届けできるようになってきました。
そんな1年間を経て、改めて禾の養鶏の適正規模について見直し、次年度は少し鶏の羽数を少なくしてみることとしました。それは販売できるたまごの量に合わせてとは一概にもいえず、調達できるエサの材料の量、鶏舎のスペース、雛を育成するスペース、私たち家族の暮らしとの兼ね合いなど、総合的に考えた結果です。今後柔軟に変化していくものとは思いますが、今度は去年とは逆に、もしかしたら求めていただける量に少し足りないかもしれないという不安を少し抱えています。
そんな中、販売方法についても度々考えてきました。特に貴重な意見をいただいたのは、宮島で自然農を営む中岡農園の山本さんご家族です。野菜の販売方法をベースに、禾にとって適切なたまごの販売方法や経営について、哲学について、たくさんのご意見をいただきました。どこか価値観が似ていて、このやり方なら私は私らしく無理なく、お客様にも満足いただけるものができるかもしれないと思いました。ただ、一方で、うまく運営できるのだろうかという不安もあり、なかなか踏み出せませんでした。
そうこうしているうちに1年が経ち、いよいよたまごの数に余裕がなくなってきたここ数ヶ月で、とにかくやってみようと決心したものが、このたまご定期便「まるごとコース」です。
鶏がたまごを産む量は通年一定ではありません。季節の変化に敏感に反応する生き物であり、そのように変化できる環境にするということを私たちは重視しています。ただ、そんな変化を踏まえると、今までの定期便では、定員上限は一番少ない季節になります。1年間、確実にお届けできるたまごの量でしかお受けすることができないからです。そうすると、多く産む春先はたまごが余って販売に頭を抱えることになりますし、少なくなる季節にはたまごが足りるだろうかと不安になります。
たまごの多い春は、本来喜ぶべき時です。その期間はきっとお祭り感覚でイベントやお店で販売ができれば楽しいのかもしれません。しかし、私にはそれがちょっと苦手です。このたまごをどうしようかとつい悩んでしまいますし、春というのは農家にとってはとても忙しく、販売よりは生産に注力したい時期です。そのため、できれば多い時に多くお届けし、少ない時に少なくお届けする、というのが理想の定期便の姿になります。旬の春に頭を抱えるのではなく、定期便のみなさまと一緒に旬を喜べるように。たまごが少ない時には、少なくてどうしようと不安にならずに、たくさん産んでくれた鶏に感謝し労われるように。それがきっと私の目指す姿なのだと気づきました。そしてそれは、受け取る方にも新しい体験になるかもしれないとも感じました。
さらに話を進めると、たまごを1年も産むと廃鶏と呼ばれ屠殺されます。1年なんて早いね?!と思われるかもしれませんが、それがたまごを産む鶏が販売に最適なたまごを産む期間の一般的な寿命ですし、スーパーなどで売られている鶏肉はもっと短い数ヶ月の間に精肉されています。それに比べると1年という長さは鶏肉の食べ頃からは長すぎて、柔らかさではなく硬さが際立ってしまうのです。そのため、なかなか一般的には出回っていませんし、加工用に使われることがほとんどです。ただ、たまごを食べるその先には必ず親鶏がいますし、硬いと言っても、1年以上健康に動き回った鶏のお肉はしっかりと味がして美味しいものでもあります。1年間たまごを産み続け、最後にはその命も差し出してくれている鶏の存在がなかなか知られていないことに、少し歯痒さを感じ、この親鶏のお肉も定期便に入れてみたいと考えました。
こうして、こんな形があったらいいなと思う定期便を考えつくも、私自身、これをうまく運用できるのかちょっと自信がありません。何度考えても、これで大丈夫と思える形にならないのです。それもそのはず、私ですらよくわからない鶏のリズムだからです。もちろん今までの定期便もみなさまのご意向100パーセントでもなく、毎月決まった量を、決まった曜日に、というのはみなさまのご協力のもと成り立っていました。ただ、それは鶏のリズムではなく、私のリズムに合わせていただいていたのだと思います。私の予想がつく範囲のたまごの量を定期便としてお届けしていました。さらに、これを鶏のリズムに、となると、私自身もどう転がるのかわからないのです。それでも、それもちょっと面白そうですし、どちらにせよみなさまにご協力いただくのなら、私よりは鶏に合わせるほうが楽しいかもとも思います。結局は始めてみないとわからないということでえいやっとやってみることにしました。
そんなこんなで、なるべく1年間は変更なしでいきたいとは思いますが、今後、鶏とみなさまと私の塩梅で変わっていくこともよしと思っています。我が家はこれでも大丈夫かも!と思えたら、お付き合いいただけると嬉しいです。
近藤温子