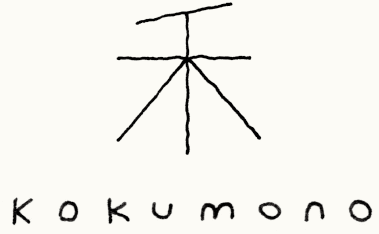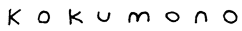禾の加工品あれこれ
2022年11月24日
禾の穀物をつかっていろいろな方が加工品をつくってくれています。
何をつかって、どんなものを、誰がつくっていくれているのか、まとめてご紹介します。皆さん素敵な人たちで、つくるものはどれもほんとうにおいしいです。機会があればぜひ召し上がってくださいね。
(長くなってしまうので敬称略です)
●米
・ササニシキ・亀の尾(うるち米)|麹・味噌|藤原みそこうじ店(鳥取)
毎年お味噌や麹にしていただいています。
・亀の尾(うるち米)|玄米煎餅|日比谷米菓(東京)
前シーズン、玄米煎餅をつくっていただきました。ほんとうにおいしかったし、禾でも一番人気の商品だったと思います。ただ先日、ぜひ今年もお願いしたいですとご連絡したところ、職人さんから体調を崩してしまったと聞かされました。再開できたらご連絡をいただく予定ですが今後どうなるかわかりません。ご高齢の方なので心配です。回復を心から祈るばかりです。
・こがねもち・太郎兵衛糯(もち米)|玄米餅・白餅|のぎ屋(鳥取)
前回も書いたとおり、昨年もつくってもらった玄米餅に加えて今年は白餅もつくっていただく予定です。我が家でも冬の定番お手軽ごはんです。
●豆
・サチユタカ(白大豆)|味噌、豆腐、黄粉||藤原みそこうじ店(鳥取)、小屋束豆腐店(岡山)、サンデールーム(群馬)
一番幅広くつかっていただいているのがこの白大豆です。他にもお味噌づくりのワークショップでたくさんご利用いただいたりもしています。毎年ほんとうにありがたい限りです。大豆の栽培はいろいろな面で難しいのですが、どうにかいい形で続けていけたらいいなと思っています。
・ヤブツルアズキ(小豆)|味噌|藤原みそこうじ店(鳥取)
今年初めての栽培と収穫でした。これからどんな形になっていくのか私も楽しみです。
●麦
・小春二条(大麦)|味噌|藤原みそこうじ店(鳥取)
今年初めての栽培と収穫でした。これからどんな形になっていくのか私も楽しみです。この小春二条は他にも、友人と一緒に麦茶をつくる計画も進めています。こちらもどうぞお楽しみに。
・スペルト(古代小麦)
50グラムからはじめて4年間せっせと種を紡いできました。この秋に種を蒔いた分がうまくいけば、来夏それなりの量になって何かにつかってもらえそうです。私もまだ口にしたことがありませんが、誰と一緒にどんなものをつくっていけるのかとても楽しみです。
●番外編
・ササニシキ・亀の尾(うるち米)、サチユタカ(白大豆)|はじまりの味噌|藤原みそこうじ店(鳥取)
・ぼくたちは夏に味噌をつくる(冊子)|真鶴出版、鈴木大輔、山田将志(神奈川)
藤原みそこうじ店さん、真鶴出版さんを中心としたチーム真鶴の皆さん、そして私たち禾。この三者で「はじまりの」という取り組みをやっていて、その第一弾がこの「はじまりの味噌」です。禾は原料としてのお米と大豆をつくる担当で、このお味噌にあうものは何かと毎年異なる品種のお米を育てて試しています。それを藤原さんがお味噌にして、真鶴の皆さんが広くお届けするための冊子やパッケージをつくってくれています。もともと本も好きなので、これはとてもとても楽しい活動です。またなにかつくれたいいなと思っています。
・・・・・
こうしてまとめてみるとたくさんありますね。穀物という枠のなかで毎年少しずつ種類や品種を増やしていって、その収穫物を扱ってもらえるつながりも増えていきました。穀物に絞っていたからこそいただいたご相談もあったので、それもうれしかったです。地味だけどすごいですね、穀物!
田畑ではいつもひとりなので、そこを離れたとき誰かと一緒にものづくりができるのはすごくうれしいです。加工品はもちろんだし、それ以外でもなにかあったらぜひご一緒できたらいいなと思っています。
近藤亮一

今年のもち米のことを
2022年11月18日
今年はもち米がたくさんあります。昨年に比べて作付面積もグッと増やしたし、ありがたい豊作でした。
今年が特別なのは品種がふたつあることです。昨年も育てていた「こがねもち」、そして「太郎兵衛糯」です。同じもち米といっても、それぞれの個性があります。
まずは「こがねもち」。1943年新潟の試験場で「中新糯40号」として生まれ、その後「こがねもち」と命名されました。稲姿は背丈が短く線は細くスラッとした印象でしたが、秋にはたくさんのお米がたわわに実る稲でした。ねばり、コシなども整っていて純粋においしいなって思うお米でした。

それから「太郎兵衛糯」です。安土桃山時代の慶長年間、いまの埼玉県で会田太郎兵衛さんがいいもち米の選抜に成功したことからはじまるお米です。この時代から品種育成に関する資料が残りはじめていて、育成者のわかる最古のお米とも言われています。稲姿は背が高く太く力強い印象で、秋にはきれいな黒い毛のあるお米が実りました。独特のつよい風味があり糸を引くほどのねばりがありました。

それぞれ異なる美しさやおいしさがあって、田んぼで見ているだけでもうれしいです。ただ育てる品種が増えるといろいろな管理が大変になってしまうので、来年はどちらかひとつに絞ろうと思っています。私たちも春までに食べ比べていきますので、お好みやご意見などあればぜひ教えてください。
それと今年はおもちの種類もふたつです。昨年もご好評いただいた玄米餅に加えて、白餅も搗いていただけることになりました。おもちを搗いてくれるのは鳥取の友人「のぎ屋」さん、いつも本当にありがとう!今年、いい白餅をつくるために新たに設備投資をされていて、玄米餅と白餅でそれぞれにあった餅搗き機をつかうそうです。すごいこだわりです。

そんなわけで、もち米もおもちも、お取り扱いいただける方やお店をたくさんたくさん募集しています。少量からでも承りますのでぜひご相談ください。もち米はいつでもお届けできますし、おもちは12月初旬頃からのお届け予定です。事前にお声がけいただければ、その分も多めに搗くことができるのでいつでもご連絡ください。
冬のお供に禾のおもちをどうぞよろしくお願いします!
近藤亮一

小さな目標に届きました
2022年11月17日
2018年の秋、独立準備をしているときに、行政が定める認定新規就農者の申請をしました。
地域の農協さん、普及指導員さんや先輩農家さんたちに助けていただきながら向こう5年間の営農計画書をつくり、何度かの面談を経て無事に認定されることになりました。その稲作に関して、目標として書いた面積あたりの収穫量に4年目の今年初めて届きました。いま心のなかに静かな達成感が満ちています。
近しい人はみんな知っている話ですが毎年の収穫量はとても厳しいものでした。虫に食べられたり草に覆われたりで細々とした稲、そして病気で赤黒く染まってしまった田んぼをずっと見てきました。稲がたわわに実り黄金色に染まる田んぼ、小さい頃から当たり前のように目にしてきた田んぼの風景は自分にとっては当たり前ではありませんでした。今年はどうだろうと期待を抱いて働く春夏を超えて、現実を突きつけられる収穫の秋は怖い季節でもありました。
これまでのことは肥料を入れないからとか農薬をつかわないからとか、そういう話ではありません。技術も経験も乏しく、純粋に農業者としての自分が至らなかったからです。それでも、実ってくれた少ないお米をおいしく感じたし、食べてくださる方からもうれしい声をいただけました。比喩表現ではなく文字通り田んぼやお客さんたちに支えられて、気持ち的にも経済的にもどうにか続けてこれました。感謝しかありません。いつも本当にありがとうございます。
今年目標に届いたといってもささやかなものです。それに試してみたいことがまだまだたくさんあります。その先の結果はわかりませんが、こんな風に思えること自体がきっと幸せなことなんだろうなと思います。これからも稲と自分にとって心地よい関わりを求めていって、そうしてできたお米で誰かとつながって、自分たちの小さな暮らしを続けていけたらうれしいです。
近藤亮一