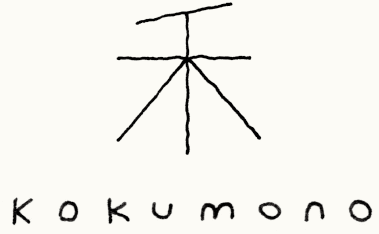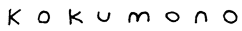お米の価格改定について
2025年08月19日
今回はお米の販売についてお知らせです。今秋収穫をするお米(うるち米のササニシキと亀の尾)から、価格を上げさせていただこうと思っています。
|玄米800円/kg→900円/kg
|白米900円/kg→1,000円/kg
ご負担を増やしてしまい申し訳ありません。ご家庭にあわせて、お買い求めいただく量や頻度を見直していただくなども含めてご検討いただければ幸いです。あまり直前でのお知らせではそうしたことも難しくなってしまうかと思い、すこし先のことではありますが早めにお知らせをとこのタイミングで書かせていただきました。
—
この価格変更について長いあいだずっと悩んでいました。それが必要だと感じてしまうのは物価が上がり生活によりお金がかかったり、どうしても必要になる諸経費も毎年のように上がったりしているからです。そしてできればしたくないと思うのは、やはり食べていただく方へのご負担が増してしまうためです。
みなさんご存知のように、ここ最近の米価高騰以前にはわたしたちのお米は一般的なお米よりも高い価格でした。それは一般的な栽培方法に比べて基本的には収穫量が少なく、また作業量が多くなるため管理できる田んぼも増やしにくいためです(もちろん人によりけりですが、概ねそうした傾向にあるとは言っていいと考えています)。しかしそれをもってして、お前の米は都市にいる金持ち相手の商売だな、といった趣旨のことを幾度となく言われたことがあります。
そんな風に思われているんだ!という驚きと困惑で、初めのうちは何と返せばいいのかもわかりませんでした。ほとんどの場合では批判と揶揄と冗談が入り混じったようなトーンで、たわいもない会話のなかにスッと入ってくるので、そういうときのわたしはだいたいすぐには反応できず尾を引くようなモヤモヤをずっと抱えてしまいます。それでも何度か経験するうちに、心の準備もできるようになって、そういうわけではないと思っていますよとお話できるようになりました。
収入の多寡がそうであるのと同じようにお金の使い道も人それぞれです。家につかう、身につけるものにつかう、好きなものや趣味につかう、自分の学びや子どもの教育につかう、ほんとうにさまざまです。お金は手にするときもつかうときも、きっとその人らしさみたいなものがよく現れるのだと思います。
わたしたちのお米はたしかに高価であるものの、お金が余って余って仕方ありませんみたいな特別な人ではなく、食や農に対してより強い興味関心をお持ちなだけの、ふつうに働くふつうの人たちがそれぞれの理由でそれぞれに限られた生活費のなかから選んでくださっているのだと思っています。それはわたしたち自身もそうだからです。
わが家も、お米や卵など自分たちでつくっているものを除けばふつうの家庭です。穀物は農作物の収穫量がずっと不安定で、豊作の年には落ち着くけれど不作の年には一気に苦しくなるし、養鶏は子どもたちとの関係でそもそもできる年もあればできない年もあります。農家になってから、例えば貯蓄ができるほどの余裕を持てたこともありません。家は格安でお借りしているし、ほぼすべての農機具は中古をなおしなおしつかっています。
そんななかでも、食べるものに関しては特別な意識を持っています。野菜、お味噌やお醤油、お豆腐にパンに珈琲などなど、この人がつくってくれたものを食べていたいと思うものがあります。品物の安さには心から感謝をしつつも、そうではない理由で選べるものを少しずつでも選んでいくこと、それはいい生活だなと感じています。
それなのに、ただ自分たちのためにと価格を上げて、まわりの方々のご負担を増やしてしまうことを心苦しく思います。その一方で、誰かが価格を上げるという話を見るときに困ったなとか嫌だなとか、そういうことを思ったことがありませんでした。みなさん悩みに悩んだ末に、もう仕方ないという判断で値上げの決断をしている姿を見てきたからです。だからこそ自分もむしろ積極的に、値上げいいですね、これからもつくってください。という気持ちが湧くほどでした。
わたしたち禾の活動も同じように思っていただけるのか、それはわかりませんが、これからもこの営みを安定して続けていくためにどうぞご理解をいただければ幸いです。
写真は、自分たちの田んぼに入る川の水がどこからきているんだろうねと、息子と一緒に山に分け入ったときのもの。軽トラックで行けるところまで行って、そこから更に奥深く30分ほど道なき道を歩いた先に、空がぽっかりとあいて光が差し込むすこし開けたところがあります。そこは澄んだ水がちょろちょろと地面から湧き出てくる、川の出発点のひとつになっています。凛とした空気が流れているわたしの好きな場所です。

今年の玄米煎餅について
2024年02月06日
今年のお煎餅は昨年までと比べて、生地の膨らみが少なくて割れやすく薄いものになっています。味は変わらないと思っていますが、食感がすこし違ってギュッと詰まった印象です。
これはどういうことかなぁと日比谷米菓さんともお話をしまして、
・日比谷さんが生地をつくれなくなったため、他の方に生地づくりをお願いしたこと
・米ぬかの量が多くて膨らみづらくなっていたこと
の2つが理由かなぁと考えています。
米ぬかが足りなかったら心配だと私がいつもより多めに送ってしまったことから始まり、いつもとはすこし違う形になったのかなと思っています。
今回それなりの長話をさせていただいて、はじめから玄米でつくると生地が膨らみづらいので、精米したお米に量を減らした米ぬかを混ぜてつくっているんだと知りました。そもそも玄米煎餅ってどうして玄米じゃなくて白米と米ぬかなんだろう?そして割合でいえば、米ぬかの量が少ないのはどうしてなんだろう?という初歩的な疑問を3年も寝かせてしまった自分に驚きです。いつもやり取りが電話なので手短に…となぜか焦ってしまって、あ〜また聞きそびれちゃったな、、ということを繰り返した結果です。
それから、こうした一つひとつをきちんと確認して、みなさまにお伝えしてから販売開始すべきところを、週末はバタバタしそうだからと焦って金曜日に開始してしまっていました。私の不手際づくしで申し訳ないこといっぱいです。
いったん止めていた販売もいまは再開しています。そしてお煎餅そのものはやっぱりおいしくて大好きな味です。お米とお醤油だけの、なんともいえない質素ないいお煎餅で、こういうものを食べていたいんだよなぁといつも思います。
同じ東京の足立区でも何軒もあった煎餅屋も生地屋もどんどん辞めてしまった。歳をとったからってのもあるけど、取引先もどんどん大手にって、それでみんな辞めていく。うちはありがたいことに玄米煎餅をってずっと注文をもらえて、これがなかったら10年も20年も前に辞めちゃったと思いますよ、と日比谷さんは仰っていました。昨年はお米が少なかったので1回しかお願いできませんが、今年も春から精一杯田んぼに向き合って、次もまたお願いしたいと思っています。そしてお米をつくっている周りのみなさまも、よかったら日比谷米菓さんに玄米煎餅をお願いしてみてほしいです。米ぬかの量はどうぞお気をつけてください。
長くなってしまいましたが、こちらご確認いただいた上で、よかったらオンラインストアにてご覧いただけますと幸いです。
▶︎お店などでのお取り扱いも募集してますので、お気軽にお問い合わせください。

玄米煎餅ができました
今年もこのご紹介ができること、ほんとうにうれしく思います。
禾が扱うものできっと一番人気の玄米煎餅。こればっかりは、お待たせしました…!という言葉が自然に口から出てきます。私も一年間ずっと楽しみにしていました。
東京・足立にある日比谷米菓さんが焼いてくださるお煎餅。原料にお米は変わらず禾の亀の尾を、お醤油は今年からは日常的に愛用している福岡・糸島のミツル醤油醸造元さんの生成りをたっぷりとつかわせていただいた、ただそれだけの素朴ないいお煎餅です。
そして今年は大変心苦しいのですが値上げをさせていただきました(税抜600円→700円)。原材料の変更や加工賃の値上げ等が理由です。これからもいいと思うものをつくっていけるよう励みますので、どうぞご理解いただけますと幸いです。
お買い求めはオンラインストアから、どうぞよろしくお願いします。
さて、ここから先はぼやきです。よかったらどうぞお付き合いください。
*****
昨年の11月。今年もぜひお願いしますと職人さんに電話したとき、体調を崩してしまってもうできないかもしれないと言われました。幸い年明けには回復・再開されて、そのタイミングでお願いできました。その間2ヶ月ほど、一年前初めてつくってもらったときのことを何度も思い出しました。「おれももう年だからいつまでできるかわからないんですけどもね」と言われて、「いやいや〜そんなそんな。ずっとお願いしますよ!」と何も考えずに答えていた自分がいました。私にはどうすることもできないけれど、その言葉をほんとうには受け止めていなかったことを後悔しました。
農家として独立してから、つくり手がわかるものへの愛着や尊敬の念をつよく抱くようになりました。ひとりの個人や小さな組織がもつ技術、信念や生き様の結果としてうまれてくるものに、大げさかもしれないけど、魂のようなものが宿っていると感じるようになりました。でもそのすごさは同時に、顔の見えるあの人になにかあれば、あるいは気持ちが薄れたり移ろったりしたらもうそれでおわりなんだという、小ささや儚さと表裏一体なんだと身をもって理解しました。
先週お電話したとき、「売れ行き次第なんですが今年は夏頃にもう一回仕込みをお願いしたいんです」と伝えると、「約束はできないけど体が動かなくなるまではずっとつくってますから、また連絡してください!」と言われました。笑いながら、でも力強く言ってくれた言葉を今度はしっかり噛み締めながら、いろいろな願いを込めて保冷庫の手前のほうにお米を残してあります。もちろん自分だってどうなるかはわからないから、大切なものをちゃんと大切に、そうやって仕事をして生きていかなきゃいけないなと思いました。