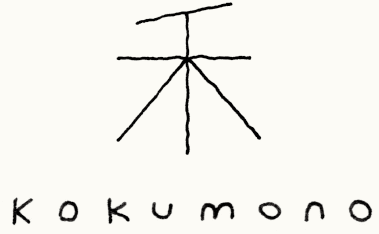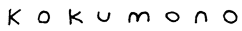2023年は大豆の年ということ
2023年07月04日
夏の農作業は体中心です。汗と雨と泥にまみれながら、空いた頭でいろいろなことを考えますが、就農5年目の今年はきっと大豆の年なんだと思いました。そんなお話です。
まず、冬に大豆の収穫用に小さな汎用コンバインを買いました。
今まではずっと先輩農家さんたちの機械を借りていましたが、申し訳ないなと思っていました。かといって自前で持とうにもお米用のコンバインと違って台数も少なく中古市場でもあまり見かけず、あっても100万以上のものばかりでした。私たちのような小さな農家には大豆収穫のためだけに用意できる額ではありません。それで、不本意ではあるけど大豆の作付面積を1〜2反ほどに減らして、手作業で刈り取り・脱穀をする小さな機械をそろえようかと考えていました。そんな悩みを聞いてくれていた移住仲間の方が、福井の中古農機具屋にいったとき、機械の山から小さな汎用コンバインを見つけて、それを私に紹介してくれました。25万円、それも簡単に出せるものではないけれど、やっていくんだと覚悟を決めれば出せる額でした。収穫物を直接排出するのではなく袋どりになっている型で、すこし手間がかかるけれど、自分の身の丈にあっているような気がしました。なにより、自分たちのものであると思うと愛着もわきます。
機械を買ったら次に困るのは倉庫ですが、お借りしている3つの倉庫は他の機械設備でパンパンです。商店を営む地元の方に相談してみたところ、隣の倉庫がきっと空いているから家主が帰ってきたら話をしてやると言ってくれました。それから数ヶ月、家主さんが帰ってきたときにすぐ話をつけてもらえました。何年もつかわれていない埃がたまっていた倉庫を掃除して、空気を通して、今更だけどシャッターの高さ足りてるんだっけ?と心配になりながら、息子がわくわく見守る中そーっと機械を入れました。ギリギリすれすれだけど大丈夫でした。汎用コンバインはバネが壊れていて脱穀部のベルトが回らなかったり、備え付けの網が大豆ではなく蕎麦用だったりでしたが、すこし手を入れれば十分につかえそうで安心しました。せっかくだから蕎麦や菜種も育ててみたいなと思いましたが、それはもう少し先の夢です。
それと今年は大豆の品種を増やしました。
今まではサチユタカという地域の奨励品種を育てていました。地元の農協で種を購入しそれからはずっと種をとっています。いい大豆ですが、岡山の在来種も育ててみたいと思って、「日の丸大豆」という赤と白のきれいなくらかけ大豆を見つけました。山形の農家さんに緊張しながら連絡をしてみて、とてもとても優しい方で、貴重な種をすこし分けていただきました。ちょうど一回り先輩で、同じ兎年の方でした。
それから、この「日の丸大豆」が岡山の在来種ってどこに文献があるんだろう?と、記事や論文を探しましたがよくわかりませんでした。どうしても気になったので研究をされている方に連絡すると、その方もやっぱりわからなくて、せまい地域にだけあったような昔の話を見つけるのは難しいですね。その方もとても優しい方で、あれこれやり取りをさせていただいた後に、17種類の在来大豆の種を送ってくれました。「ちょっと見繕って送りますね」と電話で仰っていて、2〜3種類くらい頂けたらうれしいな〜くらいに思っていたので、届いた段ボールを開けてびっくりしました。冷蔵庫に入れておけば来年でも蒔けますよ、とメモにはありましたが、いただいた種は蒔いてみなきゃ!と空いていた小さな小豆畑に急いで蒔きました。2本の紐をひいて直線と50センチの条間を出して、半月ホーで土に線をひき、そこに2〜3粒ずつ20センチ間隔で入れて、また半月ホーで土を寄せながら踏み固めていく。田植えも大豆や麦の播種も機械作業なので、こうした手作業をする機会は少ないです。でも農業の原点です。それぞれの大きさも形も手触りも違って、大豆の多様さに驚きました。
最後に、サチユタカは今年も8反ほどの作付面積です。生育はまだよくわかりません。播種前の畑の管理はタイミングを何度か逃してしまったものの、播種自体は悪くない出来でした。発芽もそれなりにそろったし、電気柵もすぐにつけられました。それでも、ひょいと出てきた芽はシカにぱくぱく食べられて、1回目の土寄せも相変わらずのいまいちな精度でした。5月の終わりごろ、耕運機で一筋ずつ土寄せするのは大変だから、トラクターにつけて速くまとめてできる機械を買えないかなと、妻にも相談して探してもらったのですが、コレと決めきれませんでした。6月の晴れが続いて土がよく乾いた日に、一日かけて土寄せをしながら思ったのは、そもそも自分の技術や感覚が未熟だということです。その作業はもちろんだし、播種前の畑の状態で決まっていることも多いです。春に整えきれなかった畑は土寄せの効きもいまひとつです。だからいま機械を変えても、たぶん根本的には良くはならないなと改めて感じました。もっと上手になりたいです。
先日、毎年大豆を扱っていただいている方から、とてもありがたいお話を頂戴しました。どうお礼をすべきか悩んで、ひとまず今はこんなことを考えてやっていますとご報告を書きました。ご覧いただいた通り、たくさんの方が気にかけてくださって、助けてくれました。大豆のご縁に感謝です。

今年もどうぞお米をつくってくださいとお願いする
2023年03月08日
雪もすっかり溶けてきて、はじまりの冬が終わろうとしています。田んぼも山も視界に映るものすべてが白く染まって、どう考えても抗いようのない大きな自然の営みの中に、この一瞬を生きているんだなと身をもって感じる季節でした。
私は米農家でありつつも、これは自分がつくったお米なんだとどうしても思えませんでした。年数を重ねるうちにどこかで身につく自信が足りていないだけだと言い聞かせてきましたが、4年目を終えてもこの気持ちは変わりません。それが先日ふと、自分がつくるわけではなく自分は環境を整えることに関わって、あとはお願いする立場にいるんだと、そんな言葉がわいてきました。いやでも農家としてこんなこと言ってていいのかな、と心配にもなりましたが、いまの私には一番納得感のある素直な表現だと思いました。
すごくふつうの話だけど自然の循環がすべての先にあります。季節が次に次にとめぐっていく力があって、それは自分が生まれるずっと前からあって、そして自分が死んでからもずっと続いていきます。その雄大な動きにあわせて、できるだけ上手にタイミングよく、自分がほしい実りの種をそっとおろして、その成長にあわせてささやかな関わりを続けていくこと。それが自分の農家としての仕事の本質です。これを言えてとてもすっきりしました。
古来から稲作が祈りと近い関係にあったことを、私は心のどこかでそれが原始的で理性に欠ける営みであるように感じていました。でも自分がずっと抱えていた違和感を突き詰めた先にたどり着くのが、ここであったのかと驚きました。
先日読んだ『気流の鳴る音』という本に「原生的な人類が文明化された人間には信じられないほどの視覚や聴覚を持っていたことはよく言われるが、そうした退化が自然や宇宙、人間相互に対して、失ってきた多くの感覚の氷山の一角かもしれない」といったようなことが書かれていました。
きっと本当にその通りで、いまの私には到底想像もできない感覚で世界と接していて、夜空の星を眺めて星座や物語を生みだすことも、祭り祈りそこに神を見出すことも、その人たちにとっては紛れもない眼前の真実であり、そしてそれはいろいろな感覚を失い知識で肥大化した私には見えていない本質だったようにも思えてきます。
春の芽吹きをそこかしこで見つけます。今年もたくさんの汗をかきながら私は私の祈りを捧げます。
写真/藤田和俊

今年のもち米と来年のお餅
2023年03月05日
先日、お取り扱い販売店さんに最後の発送をして、今季のお餅の販売が終わりました。ノートを読み返すと昨年の5倍ものお餅をつくりお届けしてきました。びっくりです!手にとってくださったみなさま、お店のみなさま、そしてお餅をつくってくれたのぎ屋の田村家にも心から感謝です。私たちも冷凍庫にストックを用意できたので来年の冬まで安心です。
そして、もうひとつ。お餅シーズンを終えたこれからは、もち米の使用量が減っていきます。これからもきちんと管理して販売を続けますが、昨年の感覚だとすべて売り切れることはなさそうだなと考えています。
—–
実は禾として農作物が次の収穫まで(きっと)売れ残るのは初めてのことです。ありがたいことに毎年たくさんの方に支えられ、すべての農作物をお届けしてこれました。私のふわっとした感覚の話ですが、生産力の伸びとお届けしていける力の伸びとが今までは不思議とバランスがとれていましたが、4年目の今年は生産力がグッと伸びたのです。
いつかこういうときも来るだろうとは想像していましたが、いざ直面するとなかなか複雑な気持ちです。販売という観点では売れ残ってしまうだろうことはやっぱり悲しいし、お米にも申し訳ないです。一方で生産量が増えたことは純粋にうれしいし、今まではずっと無くなってしまってすみませんとお伝えしていたので、なんだかやりきったような感覚もあります。
そんな両極端の想いが頭の中をぐるぐると巡りつづけ、それで、ふと思ったのです。そもそも古米って良くないんだっけ?古米でつくったお餅っておいしくないのかな?と。うるち米についていうと、実は秋から冬にかけて我が家の食卓では古米が中心になります。年間購入用にそれなりの余裕をもってお米を残しているので、秋の新米を何度か味見してからは、その残ったお米を食べています。ササニシキの古米はなんというか、しみじみとした慈悲深さを感じて、個人的にはけっこう好きな味わいです。だからもしかしたら古米でつくったお餅も、これはこれでいい!となるかもしれません。これこそがアウフヘーベン!(?)と、思い立ってから気持ちが楽になりました。
今年も小さな面積でもち米をつくるので、新米のお餅か古米のお餅か、きちんと選んでいただける工夫を考えられたらと思っています。秋までは時間があるので、もしかしたらこれからたくさんご要望があって無くなるかもしれません。それはそれでやっぱりうれしいです。でも、そうでないならないなりに、まっすぐ向き合って、素直に正直に、楽しく豊かな気持ちでご提案ができたらいいなという心の表明です。
写真/藤田和俊