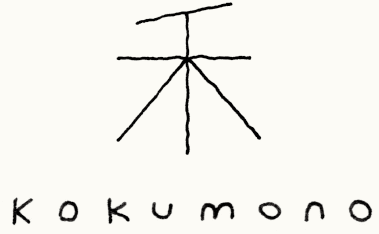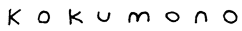[0]米と稲作の歴史をまっすぐに学んでいく
2024年12月27日
これからは田畑があるから百姓をやるんじゃない。百姓には豊かな才能と努力が必要だ。未来はそういう人間が田畑を耕す。大自然の営みを受け入れる心、土と水の力を理解し育む能力、あらゆる困難に耐え、乗りこえるエネルギー、そしてなによりも農作物への限りない愛情。それらが百姓に課せられた資格だ
漫画『夏子の酒』にて、幻のお米「龍錦」に向き合う農協組合長さんの台詞として描かれる言葉です。背中を押されるような背筋を伸ばされるようなこの言葉が、米農家2年目の冬に初めて読んで以来ずっと心に残っています。
—
わたしは神奈川県の小さな町に生まれました。会社勤めの父と専業主婦の母のもとに育ち、東京の大学を出てそのまま会社勤めをしていました。学生時代から関心のあった国際協力の仕事を志そうと決めて退職し、妻に出会い、農業に出会い、流れのままに移住して米農家になりました。
何代にも渡る農家ではなく先祖代々の土地もなく、農学部の出でもなく地元民ですらない移住者です。いま田んぼに広がる雪が解ければ米をつくりはじめてから7回目の春がきます。何年経ってもこの土地で生まれ育った人たちの身に刻まれたことはわからないままだと感じながらも、それでもなおこの土地らしさをそのままに生き写すような農作物をつくれたらと思ってしまいます。そんなときいつも、自分はちゃんとした農家であれているんだろうかという問いが心に浮かびます。資格のいらない農家の資格を、自分は持っているんだろうかと。
だからこそ自分の選んだ米づくりという営みが何なのか、どこから来ているのかをもっと学びたいと思いました。それも異なる文化や道から稲を見つめるのではなく、米の歴史、稲作の歴史をまっすぐに深く広く知りたいと。ゆくゆくは自分がこれからどうしていくべきか、どんな言葉を発していくべきか、すこしでも明らかになっていったらと願っています。そのために今はまず、日々田んぼで感じること考えることをもって、一冊一冊を身体で読んでいきたいと思います。
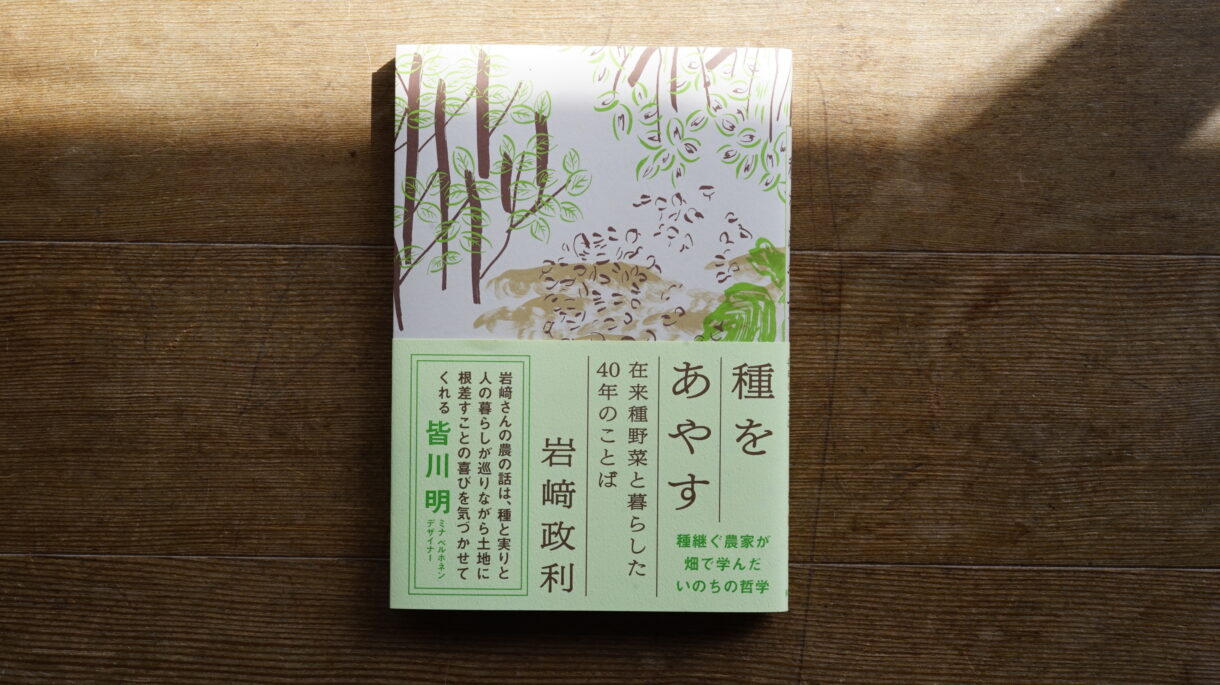
種をあやす
2023年08月18日
長崎・雲仙の岩崎さんといえば、自分たちのような農家で知らない人はいないであろう農家さんです。
大好きな野菜農家さんが岩崎さんの畑を見て野菜を食べたとき、恐縮ながら自分たちの道のずっと先にいる新しい師匠に出会ったように思ったよ、と教えてくれたのをよく覚えています。それ以来、いつかその畑に行ってみたいなという気持ちと、いやでもさすがにちょっと恐れ多いなという気持ちの両方を抱いています。
この本を読んで感じたことを、せっかくだから言葉にしておきたいと思いました。
最後のページを閉じて真っ先に思ったのは地味だなということ、そしてだからこそ、誇張も脚色もないこれが本物の言葉なんだなと思いました。岩崎さんといえば農業界のレジェンドのひとりです。先に出た農家さんは、同じ野菜農家として見て岩崎さんのすごさは作業の速さだと言っていました。自分だったら数手かかる一つの作業を岩崎さんは一手でやると。その場にいてもきっと私には見えませんが、そういう確固たる技術があるからこそ、専業農家として40年、50種類の在来種の種を採りつづけてこれたんだと思うと聞きました。そんな岩崎さんの言葉が、初めは自分が採った種に自信がなくて市販の種のなかに一列だけ蒔いたとか、種をあやす行為が恥ずかしくて人目につかないよう山や川の土手でひっそりとやっていたとかなのです。でも、というかだからこそ、十何年ものあいだ見てきた大根の花に、ある日突然深い感銘を受けたという言葉に自分も心が震えました。
「花を見て、これが野菜のもっとも美しい瞬間だと感じる心こそ、農民にとって大切なもののように感じます」
この本を端的に紹介するなら、きっとこの一節を選びます。人が食べる目的で育てる野菜の、その先で種をつなげるために咲かせる花の美しさに心を動かされることが、岩崎さんの農業なんだと思いました。
それから、野菜と穀物はぜんぜん違うなということ。穀物は食べるものがそのまま種なので、ある意味では収穫がそのまま種採りです。もちろん種採りの技術はあるけれど、自分たちのような種類の穀物農家には種を採りつづけることは当たり前の行為です。でも野菜は違います。私が唯一、家庭菜園で経験のある種採りは人参です。よい頃合いで人参を抜いて、いいものを選んで植え戻し、花が咲くのを待ってから種をとります。庭の一角が人参の白くささやかな花でいっぱいになり、なんていい風景なんだろうと思いながら、でも営農ベースでこれを続けるのは大変だなと思いました。岩崎さんも生易しいものではないと書いていたけれど、自分にはとてもとてもできません。
でもその一方で、さっき書いたこととも矛盾するのですが、なんかいいなぁって羨ましく思いました。岩崎さんが夢中になった野菜との関わりを、穀物とはまたぜんぜん違った関わりを、自分もやってみたいです。営農するほどの規模ではできないから家庭菜園として小さくでも、蒔いた種が、土から芽を出して、大きく育って、咲かせる花を一つひとつ自分も見てみたいです。畑をちょっとあけて、できれば来年の春から少しずつ、楽しみになってきました。心の動く本でした。
そもそもこの本を手にしたのは、『はじまりの味噌』についてもっと深く考えたいと思ったからでした。私が在来種の稲を育てて(いつかは大豆も)、藤原みそこうじ店さんが野生菌を採って、玄米みそをつくるこの取り組み。これまで10種類ほどの在来種の稲を育ててきましたが、その難しさや美しさもすこしずつわかってきました。明確においしくないなぁと思ってしまうことの多い在来種のお米も、野生菌でお味噌にしたら他のどんなお米でできたお味噌よりもおいしくなるかもしれません。もしそうなれば、きっと新しく残していける在来種の稲が増えていきます。穀物と野菜とは違えど、在来種とは何なのか、在来種を守るとはどういうことなのか、岩崎さんの言葉にきっとヒントがあるんじゃないかと思いました。でも読んでみての感想は、正直ぜんぜん考えが及んでいなかったな〜〜ということでした。とても長くなってしまうのでこの話はまた別の機会にしますが、どうしたものかなぁと大きな宿題を頂いた気分です。
最後に、勝手ながら写真集をつくってほしいなと思いました。大判で、その色とりどりの野菜や花を見ることができたらいいなぁと。どなたか、ぜひ!